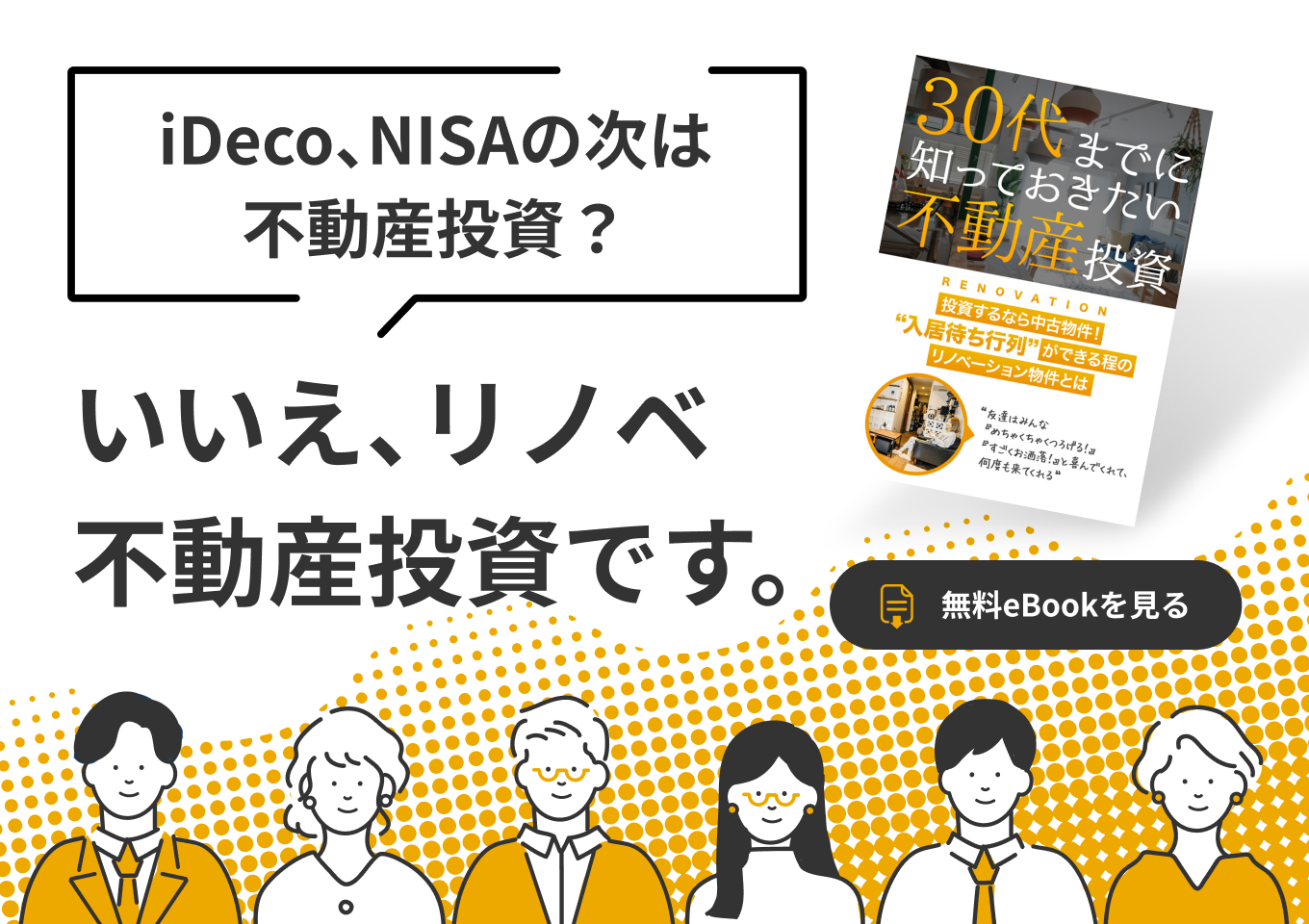不動産投資の成功率はどのくらい?不動産投資で成功する人の8大特徴
不動産投資を始めた方の中には、成功をして悠々自適に暮らしている方もいれば、失敗に終わってしまった方もいます。これから不動産投資をやってみようかとお考えの方にとっては、どんなことをすれば成功率が上がり、失敗を回避できるのか気になるのではないでしょうか。
そこで本記事では、不動産投資の成功率について、以下のようにまとめています。
- 不動産投資の成功率のデータというものは存在しない
- 不動産投資が失敗につながりやすい人に共通する6つの特徴
- 不動産投資で成功している人に共通する8つの特徴
- よくある不動産投資の種類と投資特徴を知っておこう
- 不動産投資で結果を出すために大切なこと
はじめての不動産投資では、右も左もわからない状態からのスタートですが、本記事をお読みになれば、どのようなことに気を付けていけば成功率を上げることができるのかがわかり、安心して第一歩を踏み出すことができるようになります。

目次
1.不動産投資の成功率のデータというものは存在しない
不動産投資の成功率に関する公的なデータというものは存在していません。その理由は、「成功」の定義が人によって違うためです。
成功とは、ざっくりと言えば「その人にとって価値のあるゴールをしたかどうか」です。
つまり、全く同じ時期に不動産投資をはじめても、その人が不動産投資を通じて得ようと思ったゴール設定によって、「成功した」「失敗した」と感じる感覚が変わっていきます。
高い目標をゴールに設定していれば、いくら不動産収入があっても「成功していない」になりますし、クリアしやすいゴール設定であれば、少し収入が増えただけでも「成功した」になります。
1-1.不動産投資のよくあるスタート動機4パターン
はじめて不動産投資をスタートさせるときに、第一歩を踏み出すための、大きなモチベーションとなる理由を4つにまとめています。
- 資産形成
- 年金対策
- 節税
- セミリタイアメント・FIRE
多くの方は、この中のどれかが「不動産投資をやってみよう」と思うきっかけとなり、資料請求やセミナー参加へ足を踏み出す理由となっています。
同時に、これらのモチベーションは、不動産投資のゴール設定でもあります。ゴール設定に含まれる要素は、複数の要素が混じっているケースもあります。
【資産形成】
お金を貯めたい、財産が欲しいなど、自分で資産を作って増やすことが目的です。不動産投資以外にも、株の取引・FX・仮想通貨などのハイリスクハイリターンな金融商品、定期預金や外貨預金などで着実にお金を増やすローリスクローリターンの資産形成をする方もいます。
不動産投資は、不動産という現物資産を得ながら、将来の金銭的な利益も目指すタイプのミドルリスクミドルリターンの資産形成方法です。
関連記事:投資スタート前に知っておくべき3つの投資タイプとおすすめ投資3原則
【年金対策】
退職後の年金額に不安があり、年金の足しにしようと不動産投資を始める方もいます。特に、ネットニュースなどで話題になった「年金2,000万円問題」などをきっかけに、安心した老後生活のためには、手持ち資金をコツコツ増やしていくだけでは不十分であることが周知されました。
そのため、若い方でも将来に不安を覚えて、老後の生活を支える対策の一つとして、不動産投資をスタートさせるケースも多い傾向にあります。
関連記事:「老後2,000万円」に備える。手持ちの1,000万円を資産運用で2倍にできる?
【節税】
年収の高い方が、節税目的のために不動産投資をスタートさせるケースです。主に、アッパーマス・準富裕層と呼ばれる方々で、年収が高いため所得税も多くかかります。
高収入で激務のため、預貯金がどんどん増えるのに反して、適切な資産形成対策をする暇もない傾向があります。
このようなタイプの方々が、自身のライフスタイルに合った資産形成方法の一つとして、節税目的で不動産投資を選択しています。
関連記事:アッパーマス層ってこんな人!資産・年収・生活エリアなどを徹底解剖
【早期リタイア・FIRE】
経済的に自立したライフスタイルを求める方々が注目しているのが不動産投資です。投資ができる基礎のお金を作り、それをもとにして資産を増やし、早期リタイアをして自由に生きる、今の言葉でいう「FIRE」を目的にしています。
これまでも早期リタイアという考え方はありましたが、どちらかというと、若いときにがむしゃらに働いてお金を稼いだ後は、悠々自適に好きなことをして暮らすというイメージです。そのため、大手企業の高収入のサラリーマンや事業主などの成功者などが選択するライフスタイルでした。
同じ早期リタイアでも、FIREの場合は節約と貯蓄を基本にしたスタイルなので、若くても、元手が小さくても、普通のサラリーマンでも実現可能です。
早期リタイアの達成方法は複数ありますが、現物資産として手元に不動産が残る「不動産投資」に注目が集まっています。
2.不動産投資が失敗につながりやすい人に共通する6つの特徴
不動産投資における成功の定義は人それぞれですが、不動産投資における失敗の定義は「利益が出ない」ことです。
本章では、せっかく不動産投資をスタートしても、失敗につながりやすくなってしまう方の特徴を6つにまとめています。
- 計画性がない
- 不動産会社を比較していない
- 勉強していない
- 人任せ
- 判断が遅い
- 物件選びが悪い
2-1.計画性がない
不動産投資には計画性が必要不可欠です。準備不足の状態で、「きっと、なんとかなるさ」という楽観的なスタンスではじめるのは、失敗のもとです。
基本的に、不動産投資は長期間にわたって行う投資です。長期の運用中には、家賃下落・突発的な修繕費の発生・空室・自然災害などのリスクが発生する可能性があります。
また、長期の運営をしている中で、ご自身のライフスタイルにも、転勤・リストラ・退職・病気・結婚・離婚など、さまざまな変化があります。
不動産投資をスタートする際には、物件とご自身の両方に、何かあった場合のことも想定し、危機管理を含めたうえで、長期の運営計画を立てておく必要があります。
関連記事:不動産投資の5つのリスクとは?リスクの回避策も分かりやすく解説
2-2.不動産会社を比較していない
不動産投資をスタートするときに、頼りになるのが、さまざまなシーンでサポートをしてくれる不動産会社の存在です。
不動産投資用の物件を扱う会社は、数多くありますので、複数の不動産会社の資料を見たりセミナーに参加したりして、内容をよく比較検討してから「ここは!」と思える1社を選択するようにしてください。
会社を比較しないと、例えば、おすすめされた物件価格や返済計画プラン、運営後の管理プランなどが適切なものかどうか、判断のしようがないからです。
複数の会社の資料を比較検討すると、会社ごとの特徴や、自分と相性の良い不動産会社がどこなのかがわかるようになってきますので、最低3社は資料請求とセミナー参加、できれば個別相談までしてみることをおすすめします。
適切なサポートを適宜行える不動産会社との出会いは、不動産投資の成功率を上げることは間違いありません。REISMでは、不動産投資に関した全ての期間をサポートできるだけの、ノウハウと実績があります。
2-3.勉強していない
不動産投資は、勉強不足のままスタートしてしまうと、思わぬ失敗を招きかねません。不動産投資をしてみたいと思ったら、スタート前に勉強をしっかりしてからにしてください。
不動産投資を全体的に学ぶ方法としては、まずインターネットで不動産投資関連の記事を複数サイトを横断して読む、不動産会社に資料請求をしてパンフレットなどをよく読むなどがあげられます。
インターネット上には不動産投資の種類・ノウハウ・成功例・失敗例などがたくさん公開されています。玉石混交であることを前提に読んでいけば、かなり勉強になるはずです。
不動産会社主催のセミナー参加は、以前は「本気の人しかいないのかも」という、心理的ハードルが高いものでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライン開催が主流になっていますので、少し興味がある段階でも、気軽に参加できるようになりました。
上記以外にも、複数の著者が出している書籍・雑誌の特集なども併せていけば、スタート前にある程度の知識を蓄えることは可能です。
あまりお金をかけずに学べる方法はいくらでもありますので、積極的に情報を集めて勉強するようにしてください。
2-4.人任せ
人任せ、営業担当者任せの場合は、不動産投資の成功率はかなり低くなります。
不動産投資の取引では、不動産に関した知識以外にも、金融・マーケティング・法律などの、幅広い知識と経験則が必要になります。資料などには不動産以外の専門用語も多く、最初は何を言っているか全くわからないのが普通です。
百戦錬磨の営業担当者の話を聞いているうちに、だんだん面倒くさくなってしまい「もう、全部お任せします」と丸投げしたくなることもあります。
しかし、不動産投資がスタートしたら、全ての経営責任を取るのは、営業担当者ではなく、オーナーである自分自身です。営業担当者や、セミナー担当者などにサポートをお願いするのは良いのですが、どのような情報でも、最終的には自分で調べて確認をしてから判断することになります。
判断がつかないのは情報不足が原因ですので、確信が持てるまで情報収集を繰り返してください。そのうえで、複数の不動産会社の意見に耳を傾けて判断するようにします。
ほとんどの不動産会社は業界全体のことを考えた良心的な会社です。しかし、中には、利益が期待できないような物件をおすすめしてくるようなところもあることを前提に、複数の会社から、じっくりと話を聞いていくようにすれば、失敗を回避できる可能性は高くなります。

2-5.判断が遅い
不動産投資は、一件で数百万〜数千万円という大きな金額が動く取引です。そのため、慎重に判断するのは良いのですが、あまりに慎重になりすぎると、せっかくの優良物件を取り逃がすことになります。
収益を生みやすい良質な物件は、プロの不動産投資家から初心者の不動産投資家まで、みんなが欲しい物件ですので、悩んでいる間に誰かが買ってしまいます。
会社員をしているときには、どのような場合でも即断即決はせず、上司の回答をあおぐのが普通です。しかし、不動産投資を始めたら、ご自身が経営者ですので、必要な時に適切で迅速な判断ができるだけの、情報を把握している必要があります。
2-6.物件選びが悪い
物件選びに失敗し、リスクの多い物件を買ってしまうと、不動産経営は失敗をしやすくなります。そのような物件を掴んでしまう原因のほとんどは、勉強不足・情報不足です。
例えば、不動産情報に掲載されている利回りの高さや、エリア条件を重要視しすぎ、住む人を考慮していない物件にとびついてしまうことがあります。
または、有名な会社の担当者の説明を鵜呑みにする、業界で有名な先輩投資家の言うことを鵜呑みにするなど、裏付けのない情報でも、大きな影響力がある人物に頼った結果、問題のある物件を掴んでしまうことがあります。
ビジネスデータはあくまでデータであり、物件の賃料収入が安定するためには「入居者ありき」であることを忘れると、失敗してしまう可能性が高くなります。
3.不動産投資で成功している人に共通する8つの特徴
本章では、不動産投資で成功をしている人に共通する、8つの特徴をまとめています。これから不動産投資をスタートさせる方は、なるべくこの特徴を取り入れるようにしてみてください。
- ゴールが明確
- とにかく勉強熱心
- 相場を把握している
- 欲しい物件が明確
- 判断が早い
- 絶対に焦らない
- 優秀な管理会社に委託している
- 物件探しパートナーの存在
3-1.ゴールが明確
不動産投資で成功している方は、スタートする前の段階で、不動産投資で何を得たいのか、成功することによってどんな人生を送りたいのか、つまり、ゴール設定が明確です。
例えば、年金の補填にするのがゴールなのであれば、60歳で定年退職をした後、最低でも15〜20年は安定賃料収入が続いてくれないと困ります。
そのためには、大きな家賃下落をしにくく、空室ができてもすぐに次の入居者が決まるような、駅前の築浅マンションや、中古マンションをフルリノベーションした物件などを投資対象にする必要があります。
また、中古で購入した物件を、時代に沿って生まれ変わらせることができる、きちんとした経営ノウハウを持った不動産会社にサポートについてもらうなど、長期運営前提での不動産会社探しも非常に重要です。
それ以外にも、将来、買った時よりも高い値段で不動産売却して、売却益を出していきたいと考えているのであれば、不動産価値が上がる可能性の高い、再開発地域・新路線が出来る地域などを中心にして、物件を探していく必要があります。
ご自身にとってのゴールが明確だと、自分が選ぶべき物件もハッキリしてきます。その結果、当初に決めた不動産投資で得たい結果を得やすくなるのです。
3-2.とにかく勉強熱心
不動産投資に限らず、投資で成功している方は、基本的に勉強熱心です。つぎ込んだ投資額を将来にわたって安全に守りながら資産形成をするために、常に、自分自身の情報更新を怠りません。
特に不動産投資は、不動産業界のことだけではなく、金融・法律・司法など細かなルールがたくさん関わってくるため、広い範囲での知識が必要です。
物件購入の際には、不動産売買に関する事柄や、物件の判断の仕方、ローンなどに関した金融関係の知識全般が必要になります。
経営スタート後の管理は専門会社に委託するのが一般的ですが、連絡があるときには、常に何らかの判断をあおがれる立場です。
もちろん、どのシーンでも、不動産会社の担当者のサポートやアドバイスはお願いできますが、ある程度のことがわかっていなければ、提案が適切かどうかもわかりません。
そのため、不動産経営をする方は、持っている物件数の多少に関わらず、ご自身で積極的に勉強をしているか、忙しい自分に代わって動ける優秀な右腕となる不動産会社の担当者と緊密な連絡を取っています。
3-3.相場を把握している
どんなに優良物件だと思って購入しても、その物件から想定通りの利益が得られるとは限りません。成功率の高い不動産投資をする方は、自分が想定している家賃で、長期の需要があるかどうかを、きちんと自分で調査しています。
この場所ならこのくらい、などのエリア相場以外にも、物件の広さとしての相場・社会背景の変化を想定した相場など、常に、入居者が「うん、この値段だったら」と納得してもらえる家賃相場をつかんでいます。
相場相応の賃料は、入居者にとって納得のいく値段ですので、かりに景気が悪くなっても、退居などをせずに、長期に住んでもらえる可能性が高くなります。その結果、長期的に安定した賃料収入を確保しやすくなります。
このように、相場に合った家賃設定でローンの返済計画を立てた上で、料金設定の幅を持っておくと、万が一、空室が発生した場合でも、ローン返済への影響が最小で済みます。
別の言い方をすれば、相場相応の家賃でシミュレーション計算をして、先々に利益が出なくなる可能性が少しでもあるならば、どんなに好条件だと思えても、見送ったほうが良いということになります。

3-4.欲しい物件が明確
成功している方は、どのエリアに、いくらまでなど、物件選択の条件が明確です。例えば、23区・中古20年以内・ワンルーム・駅から徒歩10分以内など、具体的な条件がハッキリと決まっています。
このような「欲しい物件の条件」は、不動産投資のゴールと深い関係があります。
ゴールがハッキリしていると、それに見合った物件が明白になってきますので、ゴールに見合った収益物件を探しやすくなり、結果的にゴール達成がしやすくなります。
逆に言えば、不動産物件情報を見ているときに、自分の条件があれこれ動いてしまうようであれば、まだ、ゴール設定が不明瞭である証拠です。
希望する条件の決め方は、先に予算・エリア・賃料収入の3条件を決め、それ以外にオプションとして付け加えたい条件をいくつかリストアップします。
希望する条件すべてをクリアする物件はほとんどありませんので、オプション条件の中で「これだけは譲れない」ものを決めておきます。
優先順位上位以外のものは、臨機応変に取捨選択していくようにすれば、希望に近い物件でありながら、ある程度の選択肢の幅がある物件探しができます。
3-5.判断が早い
不動産投資がうまくいっている方は、投資物件を見て、その物件を買うかどうかを、短時間で判断できるという特徴があります。物件選びは慎重にすべきですが、不動産投資物件の市場には、はじめたての方からプロの投資家までがいます。そのため、良質な物件ほど瞬殺で売れてしまいます。
不動産投資で成功率を上げていくためには、投資物件情報の取捨選択・現物確認をした際の投資判断が迅速である必要があるのです。
迅速な判断ができるベースには、情報量と、得た情報に対して確認ができる不動産会社というパートナーの存在があります。
さらに情報を常に更新しているため、担当者からの連絡内容で、瞬時に「買う・買わない」などの判断ができるのです。
3-6.絶対に焦らない
不動産投資で結果を出してきている方は、物件との出会いは「タイミング」が大事だということを知っています。
不動産投資を始めたら、誰もが、なるべく早く、良い物件に出会い、早く収益を得たいと考えます。しかし、不動産の場合は、まず良質な物件ありきの話ですので、希望する条件の物件が出てこなければ、そもそも買う必要がありません。
早く不動産投資をスタートさせたいと焦るあまり、納得のいっていない物件を購入してしまうと、自分が思ったようには運営できないこともあります。その結果、ゴールが遠のいてしまうことになりかねません。
不動産投資が上手くいっている方は、「良い物件はそうたくさんはない」ということをよく理解しているので、物件選びに焦りません。
特に、はじめての不動産投資の場合は、最初の1件目で納得したものを選び、可能な限り成功率を上げないと、その先の資産形成計画にまで大きく影響してしまいます。
良いと思える物件に出会えるまで、焦らず、根気よく探し続けることが大切です。
3-7.優秀な管理会社に管理委託している
はじめて不動産投資をスタートする方の多くは、会社員などをしながら、副業として不動産投資を始めます。平日は本業に時間を取られることから、建物管理や賃貸管理は自分ではできないことが多いため、専門会社に委託をすることになります。
不動産投資で成功している方は、この管理会社選びがシビアです。投資用の不動産は自分の財産でもあり、これから財産を増やしてくれる金の卵です。
財産を自分の代わりに管理してくれる会社は、優秀でなければなりません。このように考えているため、不動産投資で結果を出している方は、次のようなことをチェックしています。
- 集客力があるか
- 物件のあるエリアに詳しいか
- 費用に見合った仕事をしてくれるか
- 担当者に遠慮なく相談ができるか
特に退居があった時にすぐに次の入居者を見つける営業力があるかどうかが重要です。
特に、自分が物件から離れた場所に住んでいる場合、管理する不動産会社は物件エリアに強い方が望ましいでしょう。
委託料は1件の賃料に対しての%報酬です。毎月、固定費として出ていくことになりますので、費用に見合った仕事をしてくれなければ、経費の無駄になります。
不動産業界や不動産に関した法律やお金に関する専門的な意見が聞けるか、経営パートナーとして頼りにできるかもチェックしています。
将来、複数の戸数を経営する、または一棟マンション経営を計画している方にとっては、信頼できる不動産会社は必要不可欠です。
また、会社が良くても担当者に問題がある可能性もありますので、ネットなどで検索して資料を比較した上で、必ず担当者とも面会をしてから、管理会社を決めるようにしています。
3-8.物件探しパートナーの存在
はじめての不動産投資では、物件選びと同じくらい、どの不動産会社から物件購入をするかが大切です。不動産投資家にとって、最良の結果とは、その人にとっての不動産投資のゴールを、確実に達成できることです。
不動産会社の中には、残念ながら、あまり投資向きではない物件を、投資用物件として紹介しているところもあります。
成功するために大事なのは、これから長い期間を、不動産投資と経営のパートナーとして一緒にやっていける、信頼と実績のある不動産会社から物件を購入することです。
そのような会社は、これから不動産オーナーになる方が、不動産投資を通じて得ようとしているゴールが達成できるようなサポートをしてくれます。
REISMでは、中古のマンションに手厚いリノベーションをかけて、全く新しい価値を創造するタイプの不動産投資の提案とサポートをしています。
REISMが提唱する不動産投資物件は、入居者が「自分の好きなものに囲まれて暮らすライフスタイル」を実現できる物件です。それを実現するために、既存の物件に表面的に手を入れるのではなく、物件の骨組みだけを残して、部屋の全てをゼロから作り直すフルスケルトンのリノベーションをします。
ここまで徹底するからこそ、マンションの外観からは想像もつかない、オリジナルな物件ができ上がります。内覧をした入居者に「絶対にここに住みたい」と思ってもらえるような物件は、結果的に、長期の更新による安定収入を生み出します。
不動産投資のゴールは、設定する金額の大小はあったとしても、オーナーが求めるものは「長期安定収入」であることは同じです。不動産投資にとって最も大切なゴール達成をサポートするために、REISM は唯一無二の価値ある物件の提案をしています。
はじめての不動産投資でしっかりとしたサポートをご希望の方は、REISMをご検討ください。
4.よくある不動産投資の種類と特徴を知っておこう
不動産投資をする物件には、いろいろな種類があります。本章では、これから資料やセミナーなどで良く見聞きすることになる、4タイプの不動産投資の種類と特徴を簡単にまとめています。
- 新築マンション 区分
- 中古マンション 区分
- マンション一棟
- 土地活用
4-1.新築マンション 区分
新築一棟マンションのうちの、1室を所有することです。新築ですので資産価値が高く、少な目の自己資金でも購入できるケースが多いというメリットがあります。売却も築年数が多く残っている状態であれば、流動性も高めです。
「新築プレミア」効果で、入居者が決まりやすい点も特徴です。また建物すべてが新品ですので、修繕費はかなり先まで発生しません。
デメリットとしては、新築物件であることから物件の値段が高いことと、資産価値が下がるスピードが早いことです。新築と呼べるのは「まだ誰も住んだことがない物件」のみですので、一回でも入居者が付いた瞬間から、中古物件となります。
4-2.中古ワンルーム 区分
中古一棟マンションの中の、1室を所有することです。新築物件よりも値段が下がっているため、買いやすく売りやすいというメリットがあります。
デメリットは、経年によって徐々に家賃が下落することや、周辺に新築マンションができてしまうことで、相対的に家賃相場が下がってしまうことです。
また、徐々に修繕が必要となるサイクルが短くなる傾向があります。仮に、区分所有の部屋を良好に保っていても、建物自体が経年劣化することには、オーナーが自力で対応することができません。
ただし、フルリノベーションで物件に新しい価値を加えることで、新築区分に匹敵する値段で賃貸に出すことも可能です。
4-3.マンション一棟
マンションを丸ごと所有することです。マンションの物件は、ワンルーム・ファミリー・オフィスなどさまざまです。複数の種類の賃貸物件がある一棟物件もあります。
一棟を持つということは、土地建物すべてを所有することですので、大きな資産形成が可能です。経営面では、一棟丸ごと持つことで、空室が発生しても他の物件でカバーできるというメリットがあります。
デメリットとしては、大きな買い物ですので、大きな自己資金が必要です。売却したい時も、金額が大きいために流動性は下がります。
また、賃料収入が発生する物件が一か所に集中しているため、自然災害などが起きた場合にはリスク分散ができず、大きなダメージを受けやすいことがあげられます。
4-4.土地活用
相続などで得た不動産や土地がある場合、土地活用という方法で不動産から収益が得られるようにする方法があります。
土地活用には、マンションなどの住居を貸す経営以外にも、店舗貸し・駐車場経営・コインランドリー経営・貸倉庫経営などがあります。
しかし相続をした土地のエリアや条件によっては、どのような経営をしても良い結果にはつながらないケースもあります。その場合は、不動産を一旦売却し、そのお金で区分マンションなどの不動産投資をするという土地活用法もあります。
今後、相続の可能性があり、その中に不動産が含まれている場合は、親が元気なうちに相続に関した話し合いの場を設け、節税を視野にいれた不動産投資の提案もしてみましょう。
また、ご家族だけで判断がつかない場合には、複数の不動産会社から資料を取り寄せ、信頼と実績のある会社に無料相談をしてみるのも良いでしょう。
5.不動産投資で結果を出すために大切なこと
本章では、これから不動産投資をスタートする方が、結果を出していくために大切なことを3つにまとめています。
- 物件は立地がすべて
- 時代と人が求める物件であること
- 不動産投資のコーチ的存在がいること
5-1. 物件は立地がすべて
不動産投資物件にとっての理想の立地とは、駅近で生活に便利なエリアのことです。賃貸物件を借りる方は、利便性を優先しますので、駅から歩いて10分以内であったり、家に着くまでの間にコンビニやスーパーなどの生活に必要なものが揃う場所であることを求めています。
さらに、主要ターミナル駅にアクセスが良いことや、職場や学校にスムーズに行けるなど、便利であればあるほど、入居者を獲得しやすく、更新もしてもらいやすくなります。
周辺環境にどのような企業・大学・施設などがあるかで、ある程度、入居者層の方向性が見えてきます。はじめての不動産経営をスタートさせるときには、勉強として、気になる物件の周辺環境を自分の目で確かめに行き、入居者としての視点も養っておきましょう。
同時に、このようなマーケティングを正確に行える不動産会社からの情報提供や物件紹介も必要になってきますので、不動産情報は、複数の会社の提案するものを比較検討しておくことも大切です。
立地は、後から自分で変えることができないタイプの条件ですので、物件選びの際の最優先事項として、できる限り立地条件の良い物件から選ぶようにします。
5-2.時代と人が求める物件であること
人のライフスタイルは時代によって変わっていきます。一昔前は、なんでも新品で設備もいっぱいある物件が良しとされてきましたが、令和の現代では、ミニマリズムに代表されるように、物を大切にする・物を持たないシンプルな住まいが人気です。
不動産は必ず経年しますので、どんな建物でも、いずれは中古物件になり、かならず時代背景と合わない物件になります。中古物件が築浅物件と変わらないほどの入居率を維持するためには、多くの人から求められる「今の時代」の内装とライフスタイルを提案する必要があるでしょう。
オーナー側がそのような考え方をしていても、リフォームやリノベーションを担当する会社に理解がなければ、お金をかけても、時代に沿った物件に生まれ変わらせることは難しいので、不動産会社選びは、納得のいく結果を出すために、とても大事になります。
REISMでは、中古物件を根本からよみがえらせる、フルリノベーションという形で、何度でも不動産を再生させるさまざまなノウハウの蓄積があります。
例えば、床には天然無垢材のフローリングを採用し、入居者にはフローリングのお手入れをお願いしています。ちょっと変わった提案ではありますが、入居者による画一的ではないお手入れが繰り返されることにより、時間とともに独特の艶がある床へと成長していきます。
本来、家は少しずつ劣化していくのが普通ですから、劣化をしても自然な美しさが残せる素材を使うことで、物件ひとつひとつに個性が出ます。
良質のアンティーク家具のような個性のある物件は、どんな時代になっても、それを求める人が必ず存在します。REISMであれば、中古物件を、そのような物件に成長させることも可能です。
5-3.不動産投資のコーチ的存在がいること
不動産投資で結果を出すためには、はじめての不動産投資のサポートをしてくれる、不動産会社の存在がとても重要になります。
例えば、わからないことを何度でも勉強できる環境、融資について親身になって相談できる、優良な入居者を探してくれる管理体制があるなど、はじめての不動産投資で進んでいくステージによって、必要なサポートをしてくれる、信頼と実績のある不動産会社の存在が不可欠です。
REISMでは他では見られないような、入居者とオーナーへの手厚いサポートが自慢です。長年の経験から、入居者への満足が、結果的にオーナーの満足につながることを熟知していますので、不動産物件を所有したところからが、本格的なお付き合いの始まりと考えています。
管理面でも、一般業務とは別に、ふんわりとした入居者コミュニティや地元コミュニティを提供し、「愛着のある住まい」「愛着のある場所」作りのサポートをしています。
このような活動は、区分所有をしているオーナーが個人で行うのは難しいものですが、REISMという賃貸ブランドのファン活動のような形であれば、入居者・オーナー・会社の3者が、適度な距離を保ちながら、お互いに必要な情報をシェアしていくことができます。
6.まとめ
本記事では、不動産投資の成功率についてまとめました。不動産投資の成功率に公的なデータは存在しないものの、経営がうまくいきやすい方法があることはわかりました。
不動産投資の成功率は、ご自身が不動産投資で、いつまでに、何を得たいのかというゴール設定がハッキリすることで違いが出ます。
また、ゴール設定以外にも、はじめての不動産投資では、信頼できる不動産会社選びが、非常に重要であることがお分かりいただけたと思います。不動産投資の成功率をサポートする、不動産投資のパートナーは、REISMをご検討ください。