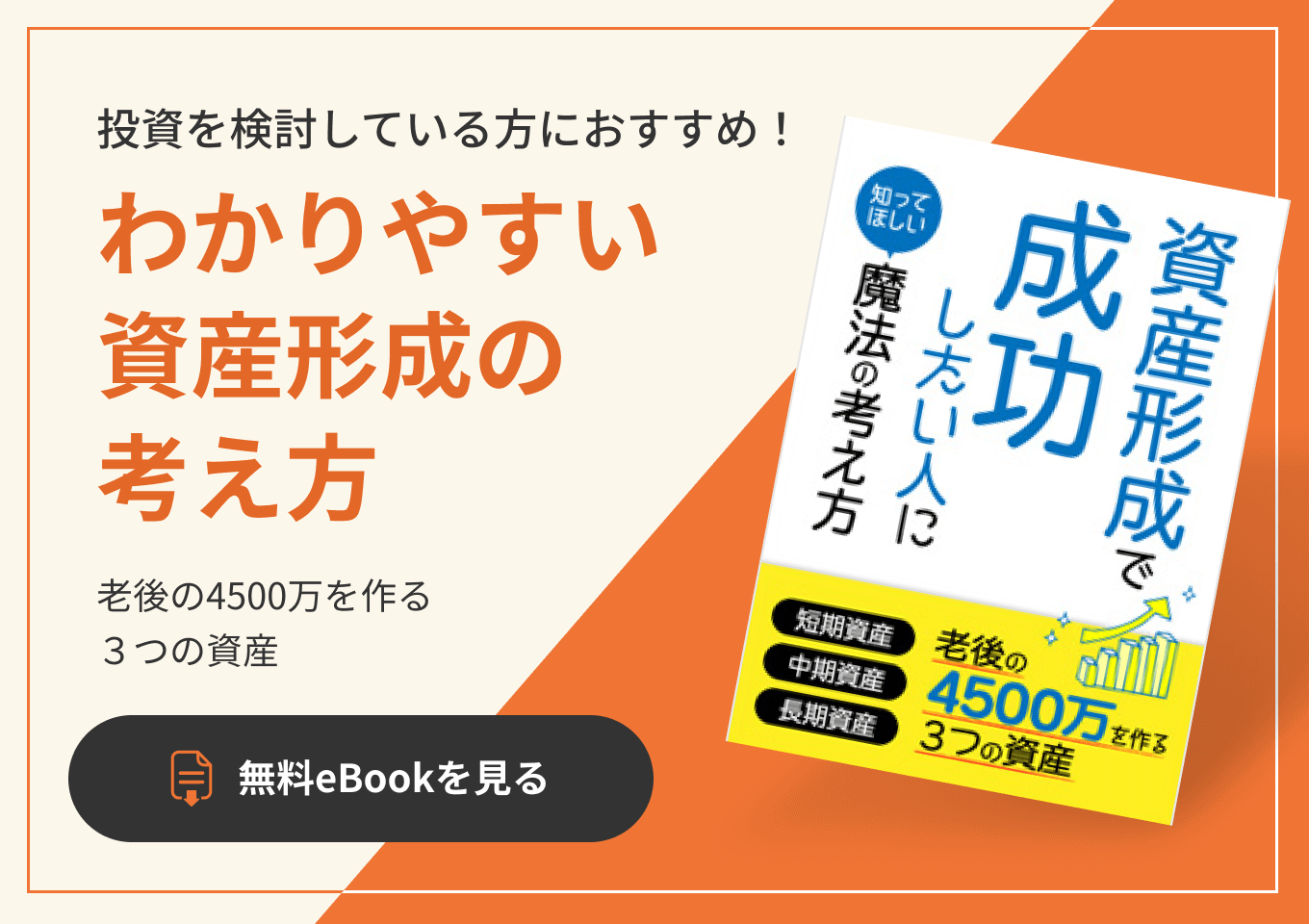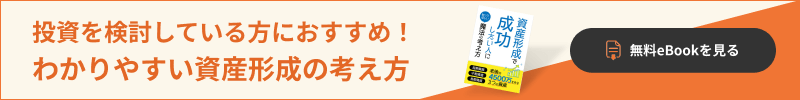不動産投資で重要な賃貸管理のポイント
不動産投資を始めると、毎月家賃が入ってきますし、購入した不動産はあなたの資産になることから、資産運用の方法として、常に高い人気を誇ってきました。また、金融機関でローンを組み、運用規模を拡大して、最終的に大きな資産を築けるという夢があることも人気を支えてきた要因と言えます。
リスクを取り積極的な投資を行えば、お金持ちになることも夢ではありません。しかし、誰でも不動産投資を始めれば簡単に成功できるというわけでもないのです。「良い物件を確保する」「入居者を見つける」「適切な賃貸管理を行う」など、長期間住んでもらうように努力することが大切なのです。

まずは物件の周辺状況をチェック
不動産投資は、物件の購入から投資が始まります。投資を成功させるためにも、購入物件の周辺状況については念入りな調査が必要です。特に、「賃貸需要と物件供給がどのような状態にあるのか」についてはしっかりと押さえておきたいところです。物件需要に対して供給過剰で、空室が目立つような地域では、せっかく投資をしても成功する確率はあまり高くありません。
競争が激しいので、物件管理や入居サポートの質をかなり高めなければならず、結果的に管理コストがかさむことになります。逆に、賃貸需要に対して物件供給が足りないエリアであれば、入居者を見つけることも比較的簡単になるため、投資エリアとしては狙い目です。また、物件のグレードを決める設備に関しても、その地域の平均的な水準は押さえておきましょう。
例えば、バスとトイレが一緒のユニットが多い地域であれば、バスとトイレ別の物件を提供するだけで、大きな差別化が図れます。最近人気の高い宅配ボックスやオートロックなどのサービスも、周囲に提供者がいなければ、かなりの差別化になるはずです。
自身だけではこうした情報の収集が難しいと感じる場合は、地元の不動産会社に協力をしてもらったり、賃貸サイトでチェックしたりすることで、ある程度の情報収集が可能になります。周辺状況をしっかり把握することは不動産投資を成功させるうえで非常に大切です。

賃貸サイトへの掲載や募集のためのポイント
物件への入居者を確保するためには、当然のことですが募集をかけなければなりません。その際、インターネットの活用と地元の不動産会社との連携が必要不可欠です。時間の許すかぎり不動産会社を回り、自分の物件について詳しく説明してください。そうすることで不動産会社の方々に印象づけられれば、入居希望者に紹介してもらいやすくなるでしょう。
多くの人たちがインターネットを活用して賃貸物件を探しています。ポータルサイトへの掲載には力を注ぎましょう。また、外観や部屋の中の写真はできるかぎり見栄えの良いものをたくさん掲載しましょう。部屋がキレイに写っていることが、興味を持ってもらうための重要な要素です。その際に、設備項目の記載漏れがないように気をつけてください。
長く住んでもらうための物件管理
こうした努力の結果、せっかく入居者が見つかっても早々に退去されてしまっては悩みの種は尽きません。退去後、すぐに入居募集をしなければならず、募集広告の費用がかかったり、空室で家賃収入が減ったりするため、キャッシュフローの悪化が懸念されます。効率が一番良いのは、入居してくれた人が、ずっと住み続けてくれることです。そのためには、物件管理が大切になります。
入居者が嫌がるのは、設備の問題と住人同士のトラブルです。その両方に素早くきちんと対応することが重要です。設備に対する不満は、予算的に対処できない場合もあるかもしれません。水まわりや電気面のトラブルは極力起こらないよう、入居者が入れ替わるタイミングで確認しておきましょう。共用部分などもこまめに清掃を行い、気持ちの良い住環境を提供するようにしてください。
なお、入居者同士のトラブルは面倒に感じるかもしれませんが、放置せずに入居者が不満を抱かないように心がけましょう。また、入居前の段階で「問題を起こしそうな方を入居させない」ということも、こうしたトラブルを防ぐうえで大切なことです。そのためには入居審査をおろそかにせず、きちんと相手を観察し、判断しなければなりません。
早く空室を埋めたくて入居審査をおろそかにすると、かえって損害を大きくしてしまう場合もありますので注意してください。最後に、何よりもそうした管理をきちんとしてくれる管理会社を見つけることが重要です。不動産は「管理を買え」というぐらいに「賃貸管理」が大切です。ぜひ信頼できるパートナーを見つけてください。