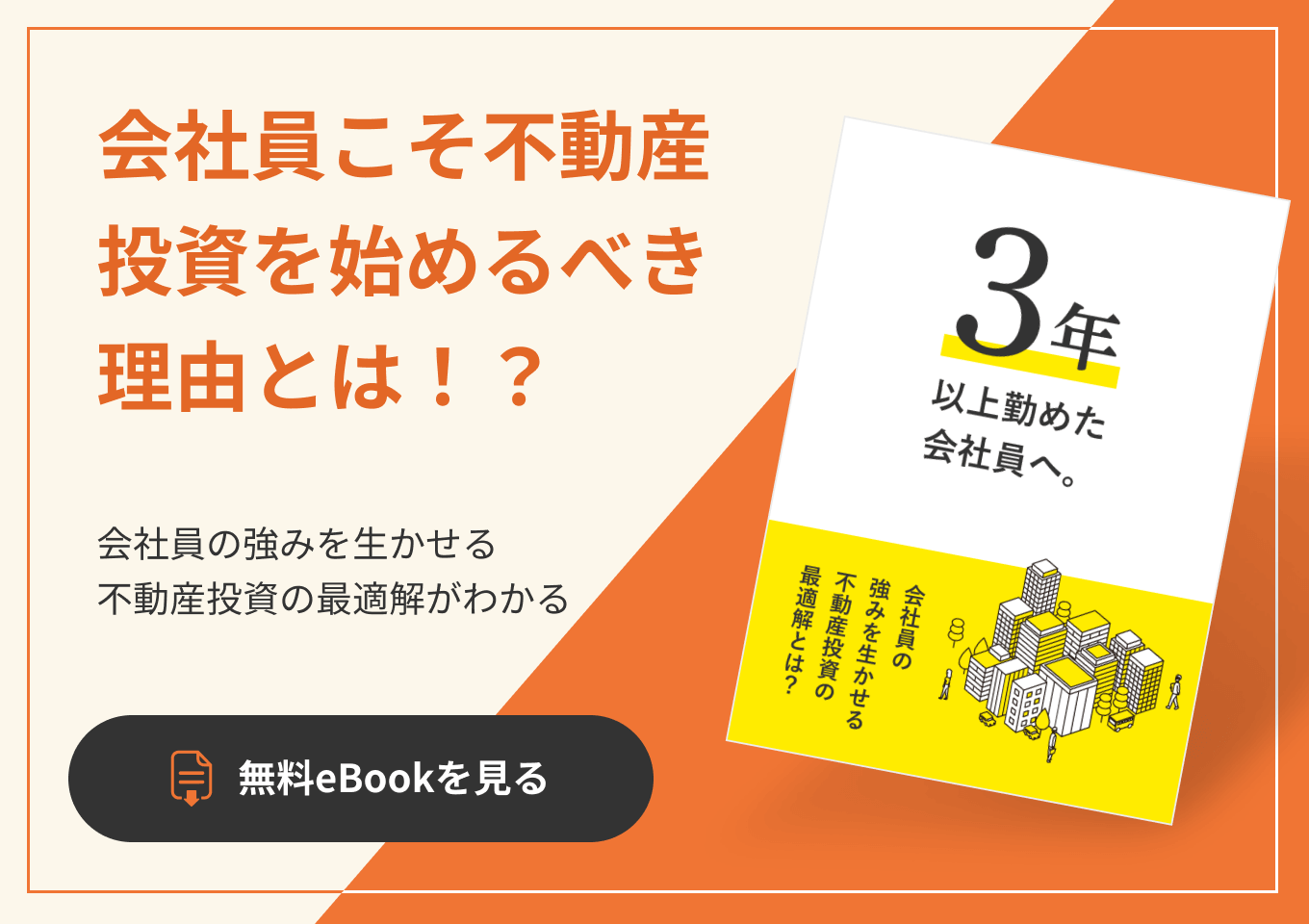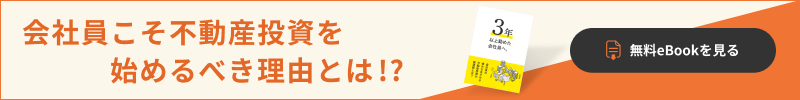「会社辞めたい」モードに入ったら作る3リストと人生逆転する4行動
「会社、辞めたいな」と思っていても、実際に辞めるまでにはさまざまなハードルがあり、せっかく入ったし、悪いことばかりではないし、次の職はどうしよう………と、なかなか決心がつかないものです。
そこで今回は、「仕事辞めたい」モードになってしまった人にとって、これからどうするかを考える際に役に立つことを次のようにまとめました。
- 多くの人が「会社辞めたい」モードになる4大理由
- 「会社辞めたい」モードになったら作る3つのリスト
- 「会社辞めたい」から人生逆転につながる4行動
最後までお読みいただければ、自分が会社を辞めたい理由がハッキリしてきますので、やっぱり頑張る・やっぱり辞めるなど、悩んでいた状態から、次の行動に移ることができます。
また、辞めるにしても残るにしても、これからもずっと続いていく「働く」こと全体を通じて、自分が本当に幸せになるためには、何をすれば良いのかもわかっていきます。

1.多くの人が「会社辞めたい」モードになる4大理由
本章では、多くの社会人が「会社を辞めたいな」という気持ちになってしまう4つの理由についてまとめています。
- 人間関係が悪い
- 労働環境が厳しい
- 給与が安い
- 社風・経営方針が合わない
1-1.人間関係が悪い
会社を辞めたいと思う理由の多くに、職場での人間関係があります。よほど特殊な仕事でもない限り、仕事をするには毎日、社内外のさまざまな人との人間関係が発生します。
たとえ苦手な相手や嫌な相手であっても、仕事を円滑に進めるためには関係性を良好に維持する必要があり、毎日のことですので、かなりストレスがたまります。
人間関係は双方に歩み寄りの精神がないと良好な関係を保てませんので、誰か1人だけが努力をしても良い結果に結びつかないことも、ストレスの原因となります。
あまりにも人間関係が悪い場合は、金銭面や待遇面での不満がなくても「もう無理」だと感じ、実際に会社をやめてしまうこともあります。
職場によくある「人間関係の悪さ」には、以下の2パターンがあります。
1-1-1.職場そのものがギスギスしているパターン
自分が属している組織(課・部・チーム)そのものの人間関係が悪く、職場全体がギスギスしたムードのケースです。自分に直接的に対立するような相手がいないとしても、自分が属する集団がギスギスしていますので、毎日、殺伐とした精神状態を強いられます。
このような職場では、基本的に、気軽な会話や笑顔がありません。中には、職場内での陰湿ないじめなどがあるケースもあり、このような状態が何年も続けば、精神的にかなりのストレスがかかります。
1-1-2.上司との関係性が悪いパターン
上司との関係性が悪いケースです。仕事場である以上、どこの組織でも常に上司・部下の関係性はついて回ります。人間同士ですので相性もあり、どう頑張っても合わない組み合わせというのもあります。
しかし、そのような相性以前の問題として
- 些細な事で怒り、怒鳴り散らす
- 人を貶す言葉しか言わない
- 高圧的な態度をする
など、職場の上下関係があることを前提に、モラルハラスメントに近いことをしてくる人物が上司になると、直属の部下は精神的に強いストレスを感じることになります。
同じように良くない態度をする同僚や後輩がいたとしても、上下関係がないので言い返す・注意をするなどができますが、相手が上司の場合は、職場での立場上、自分の身を守る方法がほとんどありませんので、ダメージはかなり大きくなります。
このような状態が長く続けば、その上司のことを考えただけで、胃が痛くなる・腹痛がする・吐き気がするなどの身体症状となって出てくることもあり、酷い場合は出社拒否やうつなどの状態になることもあります。

1-2.労働環境が厳しい
勤務時間は昼休みを入れて8時間前後ですので、一日24時間の1/3を会社で過ごしていることになります。一日の大半を過ごす職場の労働環境が厳しいと、イコール、ライフスタイルそのものが厳しくなります。
労働環境が厳しい職場を、昨今では「ブラック企業」という言い方をすることもありますが、実は、厚生労働省ではこのブラック企業の定義を明言していないため、雇用側・従業員ともに自分が働いている場所の労働環境がブラックな状態なのかを理解できず、厳しい労働環境で働いているケースも見られます。
労働環境が厳しい職場とは、例えば
- 労働時間そのものが長い
- 残業が多い
- 達成困難な仕事である
- 1人が分担する仕事量が多い
- 休日がほとんどない
- 役職以上の責任のある仕事をさせられる
- 「死ぬ気でやればできる」などの精神論がまかり通っている
- 言葉の暴力や力による暴力などがまかり通っている
などがあげられます。
こういった職場に勤めていると、心身共に疲労困憊しますので、友達付き合いも悪くなり、休日は何もできずに眠って体力を回復する………など、ワークライフバランスの悪い人生となります。
気力体力があるうちは「忙しいなりに仕事の経験やスキルが上がっているし、達成感があるから大丈夫」と思えるものですが、このような生活が何年も続いて疲労が蓄積し、自分の体力の限界が見えてくると「もう無理、会社辞めたい」という状態になります。
1-3.給与が安い
給与や福利厚生などの待遇が悪いと、会社を辞めたいというよりも、より良い仕事場へ移動しようという気持ちになります。
そこそこ納得できる仕事内容であったり、自分が希望していた職種であったりする場合には「まあ、こんなものなのかな」と諦めがつく場合もあります。また、給与が少なめでも、福利厚生が良いなどでバランスがとれる間は、納得の上で働くことができます。
しかし
- 自分の働きぶりと給与が見合わないと感じる
- 会社から得られる利益が少ないと感じる
- このまま働いても給与が上がる見込みがない
などが重なると、未来の自分に希望が持てなくなるため「会社辞めたい」「別の場所で働こう」という気持ちになっていきます。
この状態で辞めずにいると、徐々に仕事へのモチベーションも下がり、仕事へのやる気がなくなっていきます。人が働く理由はお金だけではありませんが、生活のためにはある程度のゆとりを持てる賃金は必要です。
職能や頑張りに対して、適切な昇給が得られない場合には、仕事を辞めたくなるのは当然と言えます。
1-4.社風・経営方針が合わない
社風とは、その企業が持つ独特の文化や価値観のこと、経営方針とは、その企業の持つ経営戦略のことです。これらは会社側が決めることなので、個人の価値観と相容れないこともあります。
例えば、企業の持つダークな一面や、会社の存続が危ぶまれるようなルールすれすれの営業方法などが、働いているうちにわかることもあります。
しかし、社風や経営方針に関しては、そこで長く働いている人がいる以上、清濁併せのんで働いている人たちもたくさんいるのです。つまり、それができない場合は、その企業の水が合わないということになるので、頑張って勤めていても自分だけストレスが増えていくことになります。
ここは自分の居場所ではないと感じながら無理をすると「会社辞めたい」という気持ちは、どんどん大きくなるでしょう。
自分がやりたい仕事で生きていくために多くの仕事は、昼休みを入れて8時間、一日24時間のうちの30%です。つまり、人生の30%を仕事が占めているわけですから、どうせならその時間は自分が好きな仕事や納得のいくことをしたいものですしかし、好きな仕事や納得のいくことで生計を立てられるほどの収入にならない場合、どうしても、納得のいかない仕事をする必要性が出てきます。
でも、もし、もう一人自分がいて、そのもう一人の自分が生計のためのお金を稼いでくれていたら、本当の自分は好きな仕事をして生きていくことができると思いませんか?
もう一人の自分は、例えば、不動産経営という方法で現実にすることができます。副収入を得る方法としてワンルームマンションを経営し、入居者の賃料からローン返済をしてもらえば、近い将来、会社を辞めても収入の途絶えない人になることができます。
会社員という社会属性の良さを活かせば、初期投資費用が少ない状態でも、不動産経営はスタートできます。今まで通りに仕事をしながら、マンション経営のローンを完済すれば、不動産という資産と家賃収入という印税的な収入の両方が手に入り、仕事選択の自由度と人生の自由度が上がったライフスタイルが同時に手に入ります。
「会社を辞めたい」と思ったら、会社員という利点を最大限に活かすことができるワンルームマンション不動産経営を視野に入れた新しいライフステージを検討してみましょう。
はじめての不動産経営は、丁寧な説明・相談・将来設計・購入・マンション運営までを、トータルでサポートできるREISMがお手伝いします。
2.「会社辞めたい」モードになったら作る3つのリスト
本章では、「会社辞めたい」と思ったら、本格的に辞めるための行動をする前に、作ってみる3つのリストについてまとめています。
会社を辞めるのは、社員の権利ですから、実は、会社はいつでも辞められます。しかし、「会社辞めたい」モードの時は、現状が嫌すぎるあまり精神的に追い詰められた状態であり、
- 一日でも早くこの場所から逃げ去りたい
- 会社のことを考えただけで気分が落ち込む
- 辞めれば全てが解決する!
など、気持ちの部分が優先してしまっています。このような精神状態で、後先考えずに辞めてしまうと、将来、生活費や転職先などで困ってしまうのは自分です。
どうせ会社を辞めるのであれば、自分にとってもっともベストな状態で辞めることができるようにするための、3つのリストです。
リスト2 自力で解決できることをまとめる
リスト3 自力では解決できない問題の対処
2-1.リスト1 会社を辞めたい理由を書き出す
会社を辞めたい理由を、紙などに書き出します。スマホで書いてもかまわないのですが、このような精神状態の時には、紙に書く方がセラピーとしての効果が上がり、より落ち着いて自分のことを考えるきっかけにもなります。
書き出すことは、
- 職場で何がつらいと感じているのか
- 職場の何が不満なのか
- 誰が嫌いなのか
- 何が嫌いなのか
- いつから嫌なのか
- いつ辞めたいのか
- ずっと続けていたらどうなるのか
など、自分の「気持ち」「感情」の部分をさらけ出すようにしてリストを作っていきます。誰にも見られないので、何を書いても大丈夫です。
考えても出てこなくなるまで、100個でも200個でも書いていきます。リストにしてみると、同じ単語が多い、同じ人物名が多いなど、自分が職場に対して嫌だと思っていたのが
- 特定の人物なのか
- 特定の仕事内容なのか
- お金に関することなのか
- 評価に関することなのか
- 会社以外のことなのか
などが、客観的に見られるようになります。さらに、書いたものの横に、自分にとってのストレス度合いを数字で表します。例えば、以下のようにストレスを1~10段階に分けて
| 10 | 上司のAの罵詈雑言が耐えられない |
|---|---|
| 8 | 取引先のB社の担当の態度が失礼過ぎる |
| 6 | 社内の人間関係が信頼できない、すぐ噂が流れる |
など、書き出したリスト内容に、点数をつけていきます。
こうすることで、「なぜ、会社辞めたいのか」が客観的に理解でき、そのうえで、進退を冷静に考えられるようになります。
参照:EA ハーバード流こころのマネジメント――予測不能の人生を 思い通りに生きる方法
2-2.リスト2 自力で解決できることをまとめる
リスト1で出てきた内容の中で、自分で乗り越えられることがあれば、それだけをピックアップしてまとめておきます。まとめ方は自由ですので、ストレス度合いの数字の横に色や〇印を付けたり、ポストイットなどに書き出すのでも良いでしょう。
職場で、自力で解決できることとは、主に以下の二つです
2-2-1.スキルが足りない場合
職場で嫌な思いをしている原因が、自分の能力不足や実力不足である可能性がある場合は、まずは自己解決の手段として職能のスキルアップを目指します。
今はネットで真剣に探せば、無料で教えてくれる有用な動画や教材がたくさんありますので、学ぶ気持ちさえあれば、基本的なことは身に付きます。職場で足りていないスキルを埋める努力をしていくことで、徐々に周囲の自分へ対する態度が変化する可能性もあるでしょう。
また、結果的に今の会社を辞めることになったとしても、今現在よりもスキルが上がった状態で転職ができるわけですから、自分にとっては良いことしかありません。
2-2-2.環境に問題がある場合
職場環境そのものに問題がある場合は、自己解決が難しいでしょう。このような場合は、同じ環境下で働いている先輩や同期が、どう考えているのか、どんな対処方法をとっているのかを相談してみましょう。
劣悪な職場環境を好む人はいませんので、自分が嫌だと感じている職場の空気感は、同僚や先輩も同じように感じているはずです。しかし、同じ環境にいても「会社辞めたい」と思って実際に辞めてしまう人と、辞めない人がいるわけですから、対処方法が人によって違うということになります。
先輩や同僚と話し、参考になる考え方や処し方が増えれば、それだけ環境への対応スキルが上がります。また、同じように感じている人たちが自分以外にもいるということがわかれば、それだけでストレス度合いが減ることもあります。
2-3.リスト3 自力では解決できない問題の対処
リスト1.2.をクリアしても、やはり問題が解決しない場合には、職場に対して同等または強い立場にある以下3つのような場所に相談します。
2-3-1.相談できる場所 産業カウンセラー・カウンセリング
多くの会社では、社員からの個別相談に対応する窓口があります。産業カウンセラーなどの外部機関と提携をして、社員の抱えている問題ごとに遠隔的な介入をします。
主にパワハラ・モラハラ・セクハラなどのハラスメント防止が目的ですが、それ以外の理由でも、明らかに職場環境に問題があると判断した場合には、きちんと企業に報告がされます。
そのような機能がない企業の場合には、自費にはなりますが精神科や神経内科などでカウンセリングと処方箋を受けることができます。これらの機関でハラスメントや職場環境が原因による心理的なダメージがあると診断が下された場合には、診断書をもとに次項の課へ相談に行くこともできます。
2-3-2.人事・労務に相談
1のような外部提携機能がない場合には、社内の人事・労務が相談窓口となります。
会社としても、社内の問題を拾えなかった結果、仕事効率が落ちる・社員が精神疾患にまで発展する・離職者が増えるなどの事態は避けたいため、社員から相談があれば、事実確認の上で、トラブル防止のための積極的な働きかけをしてくれます。
具体的には、問題のある人物の上長クラスに配置換えやチーム再編成などを促します。ただし、配置換えなどの処置をした後にも相談者本人の勤務態度に変化がない場合には、同時に、自分自身も査定されることも覚えておきましょう。
2-3-3.ハローワークに無料相談
ハローワークは基本的には仕事あっせんの相談に行く場所ですが、転職相談という形で無料相談を受けてくれます。この転職相談のメリットは、今の自分が置かれている立場や待遇が、他企業と比較した場合に、どの程度の状態なのか?を客観的に把握できる点です。
ハローワークからあっせんする仕事先にはあらゆるハラスメントがない、ブラックがないことが前提となっているため、職場の内部調査が非常にしっかりしています。公的機関のため、民間企業のような「ブラックとわかっていても紹介する」などの行為もできません。
そのため、どのようなラインからが職場環境が悪いといえるのかという線引きを明確に持っています。今の職場と同様の規模・社員数・仕事内容の会社と比較した場合、別の会社ではどんな働き方ができるのかなどが比較しやすいため、ハローワークに転職相談をすることで、間接的に自分の置かれている立場が理解できます。
特にハラスメントがある企業の場合、社員が会社を辞める理由が「会社側にある」ことがわかると、さまざまな助成金の停止処分が下されるため、上司のパワハラなどで社員が辞めた場合でも企業が離職票に「本人都合」と記載してくるケースがあります。
このような事態を未然に防ぐためにも、会社を辞めることの周辺情報として公的機関の転職相談の利用も検討してみましょう。実際にハラスメントがあると判断された場合には、ハローワークから労働基準監督署への紹介があります。
参照:ハローワーク 職業相談会
参照:厚生労働省 労働局パンフレット
3.「会社辞めたい」モードから人生逆転する4つの行動
本章では、「会社辞めたい」と思った時から、実際に辞めるまでの期間で、上手に人生逆転できるために大切な4つの行動をまとめています。
- 辞めた後のリスクから逆算する
- 心の退職予定日を決め、転職活動をしてみる
- 不労所得を検討してみる
- 早めのリタイアメントを検討してみる

3-1.辞めた後のリスクから逆算する
会社を辞めた後に起きる、自分のリスクから逆算をして「退職」を考えます。職種などにもよりますが、退職をするリスクには以下のようなものが考えられます。
- 収入が途絶える
- すぐ転職できるかわからない
- 転職先がさらに合わない可能性
- 転職先の給与が今より低い可能性
- 社会的信用が下がる可能性
上記のようなことは、辞めれば誰にでも起きる可能性があります。そのため、上記のようなリスクがなるべく低くなるようにしてから、会社を辞めることを想定してみましょう。例えば、
- 今の会社に在籍したまま転職活動をする
- 今の会社は辞めてから、失業保険をもらって転職活動をする
- 今の会社に在籍したまま、学校に行き、それから退職をする
- 今の会社は辞めてから、失業保険をもらって学校にって転職をする
- 今の会社に在籍したまま、何か副業をする
など、今とこれから先の未来を見据えた退職プランをいくつか練っておく必要があります。
自分が望むプランによっては、今すぐ辞めるのが得策ではないことに気が付くケースもあります。自分には複数の選択肢があることがわかっていれば、熟考の上で、最も条件の良いものが選べます。
特に、大手企業や有名企業にお勤めの場合には、社会属性の良さというサラリーマン最大のメリットがありますので、
- 平均収入が高い業種である
- 安定性が認められている業種である
という条件を失ったときのリスクを十分に考えてから行動しましょう。
例えば、不動産経営をスタートする際には、大手企業のサラリーマンであれば、自己資金の多少に関わらず、比較的スムーズに融資が組めるという大きなメリットを失うことになります。
しかし、リスクを計算に入れたプランを複数用意してあれば、自分の退職後のプランに合った辞め方ができます。会社を辞める方法は、自分の人生のリスクが最も少なくなる形で考えましょう。
3-2.心の退職予定日を決め、転職活動をしてみる
今の会社を辞める日が自分の中で決まっていれば、
- 退職を上司に伝えるタイミング
- 退職を同僚などに伝えるタイミング
- 退職を取引先に伝えるタイミング
- 必要な場合は引っ越し
などを逆算してみると、いつから転職活動をしておくべきかがわかります。
転職活動中に在職であることがわかると、面接の際に「いつから来られますか?」と必ず聞かれます。自分の中で辞める日程がハッキリしていないと、次の職場にいつ移れるのかもわかりません。また、この質問に対して曖昧に応えると、計画性のない人物と判断され、採用に至らないケースもあります。
あくまで、自分の中での退職日程ですので、この時点ではまだ上司に報告する必要はありませんが、期限を切ったことで、転職と退社が具体的になります。
転職活動をしながら手ごたえの有無を確認し、今よりも良い条件で働くことが難しそうだと判断した場合には、そのまま黙って現職を続けることもできます。
3-3.不労所得を検討してみる
サラリーマンは労働所得ですので、働いている間は収入が発生しますが、働かなくなると収入が途絶えます。つまり、今の会社を辞めても、このサイクルはサラリーマンをしている限りは永遠に変わりません。
働かなくても収入が入る状態になるには、不労所得というスタイルしかありません。例えば、DVDや本の印税収入、土地や不動産を賃貸して得る不動産収入、発明品を作って得られる特許収入などが、不労所得です。
実はこの3つの中で、不動産収入による不労所得は、サラリーマンが最も有利にスタートできる不労所得を得る方法です。
サラリーマンは、金融機関から見た場合、社会的な信用度が高い社会人です。そのため、不動産経営をスタートするための自己資金が少ない状態でも、毎月決まった給与があるサラリーマンであれば、金融機関は積極的に融資を検討しますので、都心のワンルームマンションなどの比較的手ごろな値段で購入できる不動産で不動産経営を始められます。
会社員を続けながらマンションの賃貸経営をしていけば、会社からの収入はいままで通り生活費となり、購入したマンションのローンは、入居者が賃料として支払ってくれますので、自分のライフスタイルは今までと何も変わりません。
しかし、ローン完済後は、賃料はそのまま収入になりますので、不労所得となります。このようにして、サラリーマンであることを最大限に活用すれば、収入スタイルを、労働所得から不労所得へと自力で切り替えることができます。
会社員であること、ある程度の勤続年数があることが大きなメリットになるので、会社を辞めたいと思ったときには、一度、不動産経営による不労所得の可能性を考えてから、辞めるタイミングを考えましょう。
3-4.早めのリタイアメントを検討してみる
会社を辞めることを考えたとき、早期のリタイアをして、退職後に一切の仕事をしないでも良い人生の可能性も考えてみましょう。リタイアメントには
- 普通に定年退職をする
- 普通よりも少し早い退職をする
などの一般的なリタイアメント以外にも、最近、全米で話題になった書籍「FIRE」などのように、一定期間集中的に仕事と投資をして人生に必要なだけのお金を作り、自分にとって最も若い年齢で仕事とお金の問題から解放されるというリタイアメントの考え方もあります。
いつの時代にもこのような早期リタイアメントの考え方は脚光を浴びますが、今回の「FIRE」で特徴的なのは、お金持ちになることが目的なのではなく、お金を稼ぐことから自由になることが目的であるところです。
つまり、自分の人生にとって必要とされる総資産さえ得られればそれで良い、というとても潔い決断方法であり、そこには「自分にとって価値ある状態」しかありません。そのため、質素な暮らしを選択するのであれば、毎月の生活費がたったの10万円でも良い、というのが魅力です。
例えば、現在30歳の人が35歳でリタイアメントをし、35~85歳まで生きると仮定した場合を単純計算した場合には
生涯に必要な金額 月額10万円(年120万円)×50年間=6,000万円
上記の計算のとおり、約6,000万円の資産をリタイアメント開始予定の5年後まで創り出せば良いことになります。上記の例は少し極端ですが、自分の収入やライフプランなどをベースに、10年、15年などの長いスパンで考えれば、そこまで無謀なことではありません。
早期リタイアメントを考えてみる際、月額費用の全部または一部が、前項で紹介した不労所得・不動産経営によってもたらされるようにライフプランを作成すれば、より人生は快適になり、あらゆる社会情勢の変化にも柔軟に対応していくことができます。
会社を辞めたいと思ったときには、現状の職場から撤退することだけを考えるのではなく「お金を稼ぐことからも自由になる」という選択肢があることを理解したうえで、退職や転職を考えてみましょう。
参照:FIRE 最速で経済的自立を実現する方法
関連記事:不労所得とは?会社員が最速で経済的自立を実現して自由になる方法
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。「会社を辞めたい!」というモードになった時に役立つことを、以下のようにまとめました。
- 多くの人が「会社辞めたい」モードになる4大理由
- 「会社辞めたい」モードになったら作る3つのリスト
- 「会社辞めたい」から人生逆転につながる4行動
会社を辞めてしまいたい!という気持ちになることは、決して珍しいことではなく、職場環境や賃金になどに問題があれば、とても普通の感覚であることがお分かりいただけたと思います。せっかく入った会社ではありますが、あまりにも価値を感じられないのであれば、退職もひとつの選択肢です。
会社を辞めようかなというモードになった場合には、ぜひ、企業に属するというスタイルだけにこだわるのではなく、それ以外の収入が得られる方法もオンリストしたうえで、次の人生を考えてみましょう。
今回、紹介したワンルームマンションの不動産経営は、サラリーマンであることが大きなプラスに働きます。一旦、この条件をリリースしてしまうと、次に同じだけの有利な条件をそろえるのには時間がかかる場合もありますので、転職や退職を考えた際には、サラリーマンである状態のままで、不動産経営が自分にとってどれほどのメリットをもたらすかを確認しておきましょう。
不動産経営に関して何も知らない、まったくの初心者スタートからしっかり伴走してくれるREISMであれば、初めてのセミナー参加・購入方法・デザイン・運営方法までをトータルでサポートし、自分にとって価値ある資産になるように、一緒に考えて走ってくれます。
会社を辞めたい……というモードになってしまったら、まずは、不労所得や不動産経営について知ってみることから始めてみましょう。