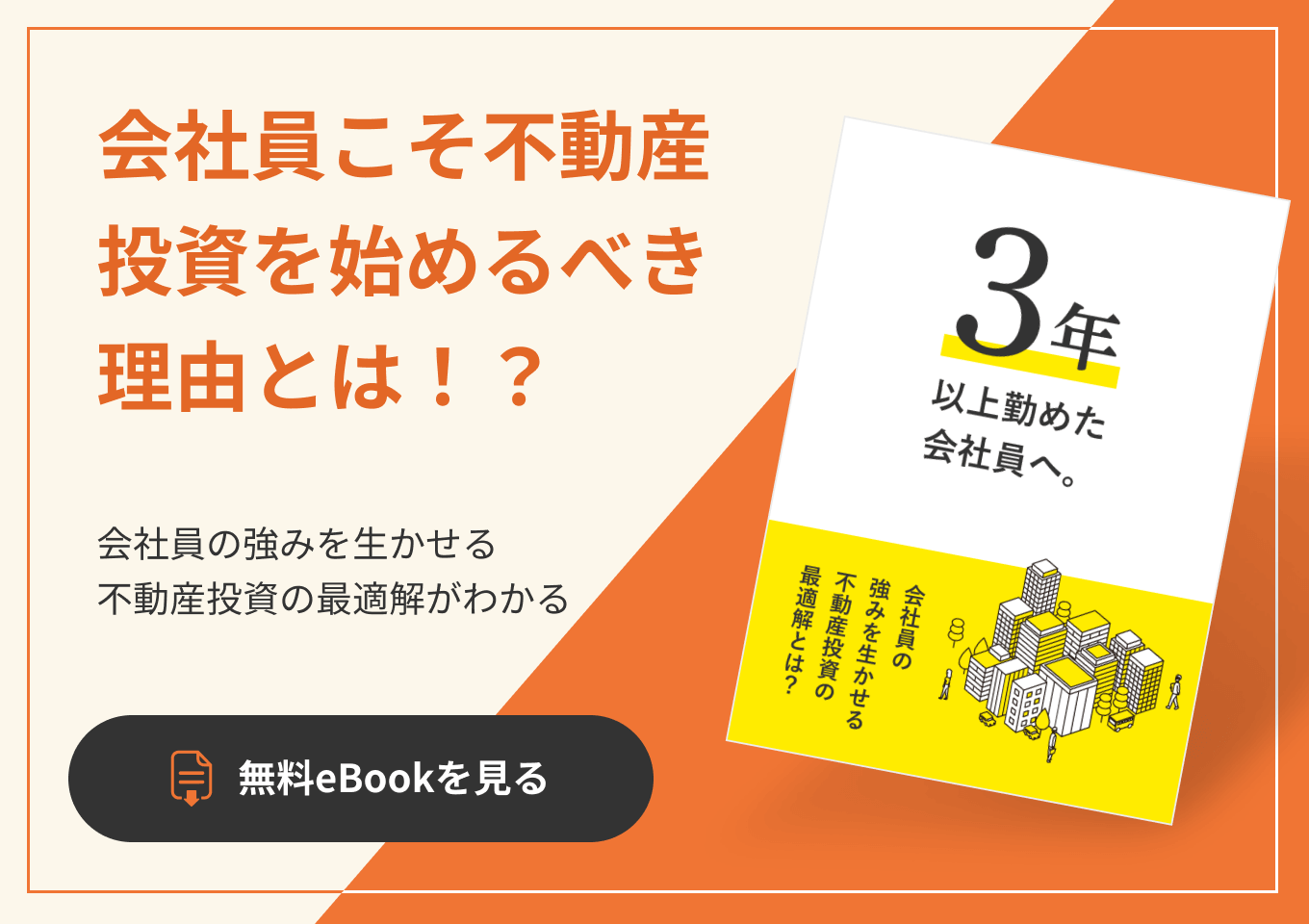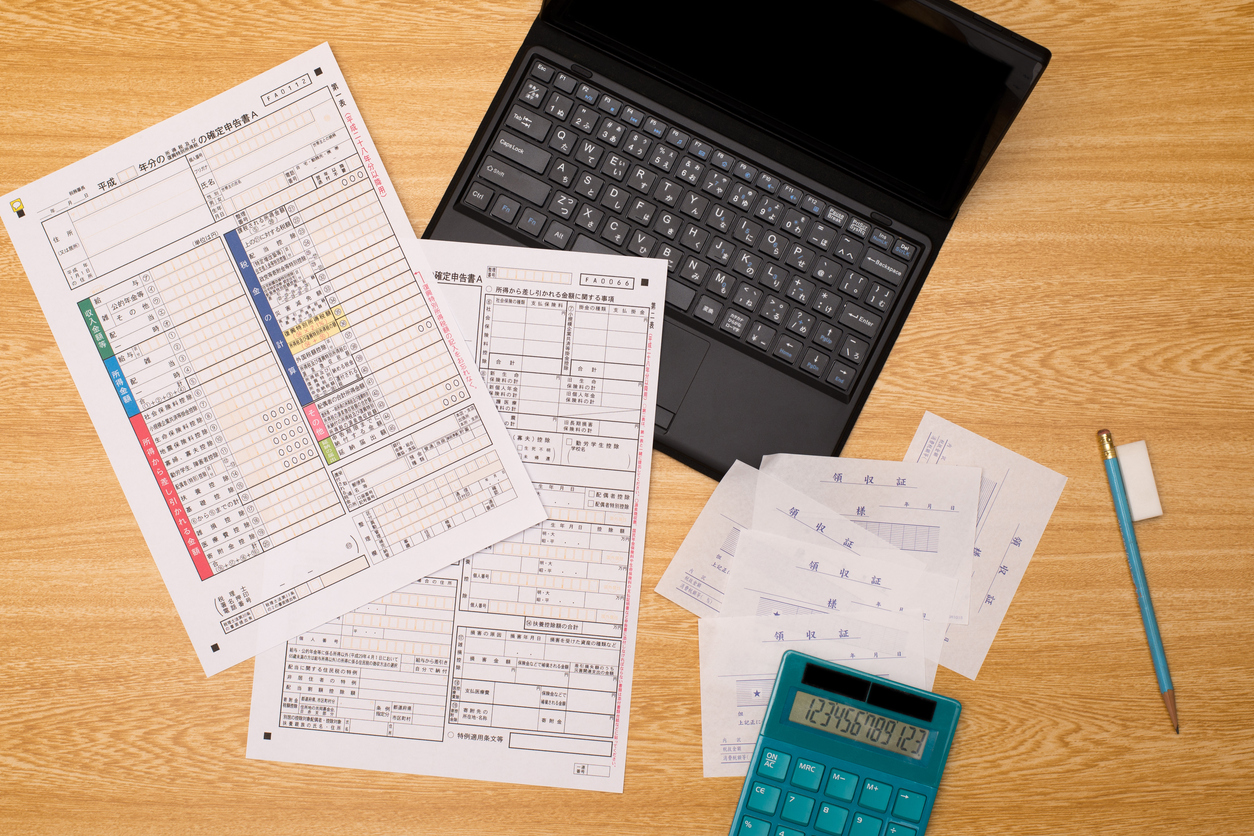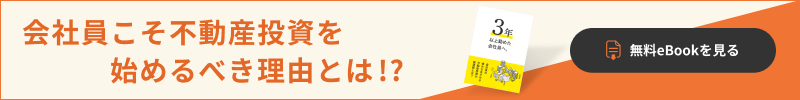不動産収入を得たときにかかる税金のすべて
不動産投資のために収益物件を取得し最後に売却して「手仕舞い」とするまでには、実にさまざまな税金がかかります。不動産によって収入を得た場合にかかる税金にはどのようなものがあるでしょうか。
大きく分けると物件を購入するとき、運用しているとき、そして売却したときの3回に税金との関わりがあります。不動産投資と直接の関係がない場合もありますが、その物件を相続した場合には相続税と関わってくることもあるでしょう。
「こんなにたくさん税金を納めている!」と知れば納税者として税金に対する意識も変わってくるかもしれません。そこで、本記事では不動産投資に関連する税金の全容を解説します。しっかりと税金のことを理解して、思わぬ不利益がないようにしてください。

目次
1.不動産を取得すると発生する税金
物件を購入することが決まり、最初の契約時にかかるのが「印紙税」です。土地や建物を買うときに売主と交わす「不動産売買契約書」や建物を建てるときに建築業者と交わす「建築請負契約書」には、収入印紙を貼ります。契約書へ収入印紙を貼付し印鑑を押せば印紙税を納めたことになるのです。
例えば取引価格が5,000万円以下なら1万円、1億円以下で3万円になります。(金額は軽減措置後で2022年3月31日までに作られた契約書が対象 )
また、不動産を売買や贈与、交換などで取得した際にかかるのが不動産取得税です。税率は不動産の固定資産税評価額の4%となります。(2024年3月31日までは軽減税率で3% )さらに取得した不動産の登記にかかるのが登録免許税です。新築したときは同0.4%、他人から取得したときは同2%がかかります。
間接税となりますが消費税も忘れてはいけません。取得した不動産の建物部分の価格と不動産会社への仲介手数料(400万円以上の場合は通常取引価格の3%+6万円)に10%の消費税がかかります。(いずれも2022年2月時点)

2.運営時に発生する税金
取得時の次には、所有している不動産を運用している段階で発生する税金について解説します。運用中の税金は「所有していること」と「利益を上げていること」に対する課税があります。
2-1.固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は、それぞれ不動産物件を「所有していること」にかかる税金です。それでは、それぞれ解説していきましょう。
固定資産税は、毎年1月1日の時点でその不動産を所有している人に課税される税金です。税率は1.4%で、固定資産税評価額に1.4%をかけた金額が税額となります。
ここで、固定資産税評価額とはいったい何なのかという疑問がわいてくると思います。固定資産税評価額を決める根拠となっているのは、総務大臣が定める評価基準です。これをもとに都道府県の知事もしくは市町村長が決める仕組みになっています。投資用マンションなど住居用の不動産ではおおむね公示価格の70%程度と見積もっておけば目安になるでしょう。
もう1つの都市計画税は、市街化区域にある不動産を所有している人に課される税金です。土地には市街化区域と市街化調整区域がありますが、マンションやアパートが建っている時点で市街化区域なので、不動産投資のために所有している物件には都市計画税が課されると考えておくべきです。
なぜなら、都市計画税の課税対象外である市街化調整区域では開発行為が認められておらず、投資用のマンションやアパートを建てることも実質的に不可能だからです。
なお、都市計画税は0.3%を上限として税率は自治体が決めることとなっています。多くの自治体は上限の0.3%を適用しているので、固定資産税と合わせて1.7%が毎年発生すると考えておくとよいでしょう。
2-2.所得税・住民税
不動産投資では家賃収入を得ることができます。これが所得となるため所得額に応じた所得税と住民税が課されます。先ほどまで解説してきた税金は所有している不動産の価値に対するものでしたが、この所得税と住民税は得られた利益に対する税金です。
所得税には累進性があるので、所得額に応じて税率が変動します。こちらが所得税の税率一覧です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得が高くなればなるほど、税率が高くなることがおわかりかと思います。不動産投資を本業にしている方の場合は、不動産収入がそのまま所得額になります。そうではなくサラリーマン大家など本業が別にあって副業として不動産投資をしている場合は、本業収入と不動産収入を合算した金額が年間の所得額になります。
例えば、本業の給与所得が年間500万円の人が不動産投資で年間200万円を得ているとします。この場合の不動産収入は経費やローン返済などを差し引いた手残りを意味します。この人は合計で年間に700万円の所得を得ていることになるので、上から4つめにある「6,950,000円 から 8,999,000円まで」のカテゴリーに含まれます。税率は23%です。簡単に計算してみましょう。
700万円 × 23% - 63万6,000円 = 97万4,000円
計算の結果、この人の所得税額は97万4,000円となりました。ここでお気づきになった方がおられるかもしれませんが、年間所得が700万円のカテゴリーに入ったことで所得税率が23%になりました。695万円以上の人が属するカテゴリーなので、あと5万円強所得が少なければ1つ下の20%になります。
こういった場合にうまく経費を計上できれば節税になるので、特に所得が高い人は税務のプロである税理士をつけて経費の計上漏れがないようにしっかりと管理をするのがセオリーです。
もう1つの住民税も、前年の所得に応じて課される税金です。所得税は国税ですが、住民税は地方自治体の税金です。所得額に応じて課税されますが、住民税には基礎控除や社会保険控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などさまざまな控除があり、条件に応じてこれらを差し引いたうえで税額が計算されます。
地方自治体によっては税額をシミュレーションできるサービスを提供していることがあるので、それらを利用して計算してみると税額を知ることができます。
ちなみに、先ほどの本業年収500万円で不動産収入が200万円のケースで、一般的な社会保険料、生命保険料、そして妻1人(専業主婦)、子2人を想定してシミュレーションしてみたところ、住民税の税額は39万2,000円になりました。ただしこれはあくまでも目安なので、この結果から「これくらいの税額になる」というイメージをつかむのに役立ててください。
2-3.個人事業税
個人事業主が事業収入を得ると、その収入に対して課されるのが個人事業税です。個人事業税は課税対象になる事業が定められており、そのなかには「不動産貸付業」や「駐車場業」があります。マンションやアパートの経営をしている人は前者に、駐車場経営をしている人は後者に該当し、事業に対する税率はどちらも5%です。
これだけを見るとなかなか重い税金のように感じるかもしれませんが、小規模な不動産投資ではなく一定以上の事業規模になった人が課税対象になります。その基準を定めているのは各自治体ですが、マンション投資であれば一般的に10室以上を運用していると対象になるというのが目安になります。
また、個人事業税には控除があります。事業を営んでいた期間によって控除額が月割りになる仕組みになっており、1年間を通して不動産投資を行っていたのであれば、最大額の290万円が控除されます。つまり、年間の不動産収入から290万円を引いた金額に5%をかけたものが個人事業税の税額となります。
2-4.消費税
私たちは日々の生活で消費税を支払うシーンが多いので、なじみの深い税金の1つです。賃貸住宅に住んでいる方ならご存じかもしれませんが、家賃は消費税の課税対象外です。ちなみに事業用の不動産物件(オフィスや倉庫など)には消費税が課税されるので、生活に欠かせないものについては税の負担を軽減するといった意味合いがあります。
ただし、入居者から支払われる消費税を非課税にするには、その物件が住宅用であることを明記しなければなりません。賃貸契約書に住居用であることを明記し、居住以外の用途に使ってはならないとの文言を入れることで、その物件に入居する人は居住を目的としていることが明らかになります。
もう1つ、賃貸期間が1ヶ月未満だと消費税が非課税にならないので、賃貸期間が1ヶ月以上であることも条件になると押さえておいてください。
さらにもう一点、不動産投資家と消費税との関わりで知っておくべき概念があります。それは、「課税事業者」です。事業者だと誰もが消費税を徴収し、納税する必要があるのかというと、そうではありません。
課税事業者にならなければ消費税は非課税で、一般的に物件を1戸所有しているだけであれば消費税の課税事業者になることはないでしょう。なぜなら、年間の売上高が1,000万円を超えると課税事業者になるという判断基準があるからです。
家賃に消費税はかからないので不動産投資家は納税の必要がなく、そして売上が1,000万円未満の不動産投資であれば課税事業者にならないため、やはり納税の必要はないという2点を押さえておけば問題ないでしょう。
3.売却して所得を得れば譲渡所得税
不動産投資の仕上げは、売却です。売却で所得を得た場合にかかるのが譲渡所得税で、譲渡所得税は長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。
売却したときの1月1日時点で5年を超える期間にわたって所有していた不動産を売却し、そこから得た所得は長期譲渡所得となり、それ以下の場合は短期譲渡所得となります。譲渡所得税の課税対象となるのは、総収入から建物の取得費用と譲渡費用を差し引いたものです。
取得費用とは、不動産を買ったときの値段から減価償却したもので、譲渡所得とは、仲介手数料や立ち退き料、建物の取り壊し費用など売却するために使った費用になります。
なお、譲渡所得は「分離課税」という方法で課税されるのがポイントです。分離課税とは、不動産貸付による不動産所得や会社員の給与所得など総合課税の所得と異なり一般の累進税率より低い税率で課税されることです。
長期と短期の場合で税率が異なります。長期が所得税15.315%+住民税5%、短期の場合は所得税30.63%+住民税9%です。(復興所得税を含む)
なぜ、このように短期譲渡所得税は2倍近い税率なのかというと、いわゆる不動産転がしと呼ばれるような短期売買で利益を狙うような投資の税率を高くすることで短期売買を抑制する狙いがあるからです。
所有期間が5年以下、もしくは長期なのか短期なのかきわどい場合や、不動産の譲渡益が発生しそうな場合以外には関わりがありませんが、該当する場合は特に所有期間に注意してください。
4.贈与や相続でも税金は発生
運用中の不動産を贈与されたり親族から相続したりした場合、それぞれ贈与税と相続税がかかります。ただし、相続精算課税制度を利用せず暦年贈与を選択している場合、年間110万円の基礎控除額を超えなければ贈与税は無税であり申告する必要もありません。
なお、受贈額から基礎控除額を差し引いた課税価格によって税率と控除額が決まります。相続税の課税対象額は以下のものを差し引くことが可能です。
- 墓所
- 仏壇
- 生命保険金
- 死亡退職金についての非課税枠
- 借入金
- 葬儀にかかった費用
この残額から相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を引いた残額が課税対象額です。一人あたりの相続税は、まず課税遺産総額を法定相続分で分割し、その金額に応じた税率をかけて控除額を引いて算出します。
法定相続による取得金額が1,000万円以下の場合は税率10%で控除額はゼロです。3,000万円超~5,000万円以下は税率20%で控除額は200万円などと金額に応じて定められています。課税対象額別の相続税率一覧は、以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように不動産投資では、収益物件を買ってから手放すまでさまざまな局面で課税されます。納税は国民の義務のため、税額を適切に計算し正しく納めるようにしましょう。また、これから不動産投資を始める人は信頼のおける不動産会社に相談しながら、かかる税金についても事前にしっかりと把握した上で投資プランを立てるようにしましょう。