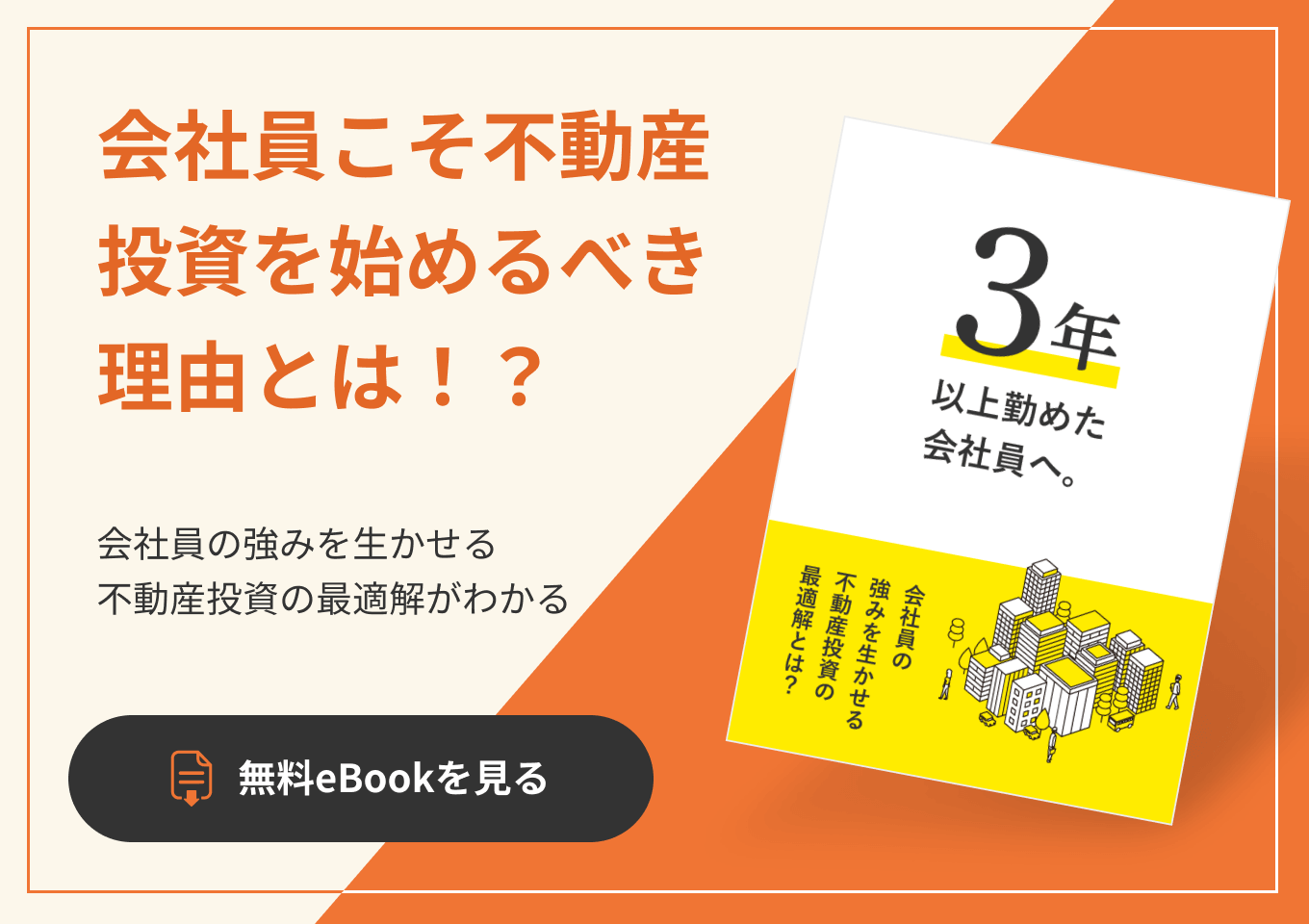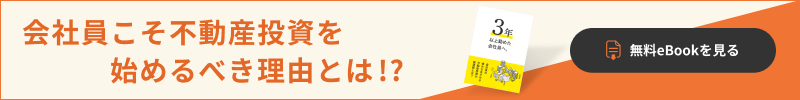初心者が不動産投資物件を選ぶときのポイントは?投資物件の種類と注意点 も解説
初めて不動産投資をする方にとって最も重要なことは、正しい物件選びです。物件選びさえ間違えなければ不動産投資で大きな失敗をする可能性は低いですが、逆に物件選びで失敗してしまうと大きな損失につながる確率が高くなってしまいます。
しかし、だからといって初心者で目利きに自信があるという人はごく少数です。大半の人は「不動産投資の賃貸物件を選ぶとき何に気をつければ良いかわからない」と悩んでしまうのではないでしょうか。
「老後2,000万円問題」に象徴されるような老後資金への不安などを受けて、岸田政権は「貯蓄から投資」の方針を打ち出しています。投資を始めるのであれば前から気になっていた不動産投資を始めてみたいとお考えの方は多いことと思いますが、不動産という高額商品を購入するだけに失敗だけは何としても避けたいところです。
不動産投資において失敗を避けるためには、不動産物件にはどんな種類があって、特に初心者に向いているのはどんな物件なのかを知ることから始め、さらに物件選びの際に価格や利回り以外の部分にも着目することが大切です。本記事では不動産投資物件の種類とともに、物件を選ぶときに注意したいポイントを解説します。

目次
1.不動産投資物件の種類
不動産投資の対象となる不動産物件には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
1-1.区分マンション
マンションを「部屋」単位で購入し、そこに入居者が入ることで家賃収入を狙う不動産投資を、区分マンション投資といいます。区分マンションに対してマンション一棟を丸ごと購入して運用することを一棟マンション投資といいますが、一棟マンションと比べると1戸単位で購入できるため、区分マンションのほうが圧倒的に少ない予算で始めることができます。
また区分マンションは流通量がとても多く、売却時にも買い手を見つけやすいメリットがあります。例えば、全部で10戸の部屋がある一棟マンションと10棟のマンションにそれぞれ1戸ずつ区分マンションを所有するのとでは同じ10戸であっても意味はまるで違います。
一棟マンションは経営の効率が高い一方でそのマンションに集中投資をするリスクがありますが、10棟のマンションに1戸ずつ所有する区分マンション投資だとリスクを分散することができます。
少額からでも始めやすく、なおかつリスク分散になる点で区分マンション投資はいわゆるサラリーマン大家と呼ばれる兼業投資家からも高い人気となっています。
1-2.一棟アパート
アパートは区分単位で売買されることがなく、売買も賃貸経営も一棟単位です。地域や物件によってケースバイケースではありますが、区分マンション1戸分の価格帯で一棟アパートが買えることもあるので、区分マンションとよく比較される不動産投資です。
1つのアパートに複数の部屋があるので満室経営になれば家賃収入は戸数に比例して多くなりますが、マンションと比べて耐用年数が短いことや不人気になってしまうと利回りが一気に悪くなってしまうリスクがあります。
1-3.戸建て
戸建て住宅を所有し、そこに入居している人からの家賃収入を得るのも不動産投資の一種です。近年では「不動産投資=集合住宅」というイメージが強くなっていますが、古くから戸建て住宅の賃貸は借家と呼ばれ、今も多くの戸建て賃貸物件があります。
ただ、最初から戸建て住宅を投資目的で建てる人は少なく、自分が住んでいた戸建て住宅に転勤などの理由で住まなくなり、その空いた家に入居者を募る形や、相続によって取得したものの居住地か遠い家やすでに家があるので使う予定のない家を賃貸に出すなどのパターンが多いようです。
2.不動産投資初心者に向いている物件
これから不動産投資を始めようと考えている人は、不動産投資の初心者です。そのため、わからないことが多く、できるだけ失敗するリスクが低い、そして取り組みやすい物件にしたいと考える人がほとんどでしょう。
そんな人におすすめなのが、中古区分マンションです。しかし、ただ中古区分マンションというだけだと差別化が難しいので、より競争力の高い不動産投資を目指す方法としてリノベーションを提案します。
2-1.中古区分マンション
先ほど解説した区分マンションには、新築と中古があります。この両者のうち初心者向きといえるのは中古の区分マンションです。理由は新築よりも安い価格で物件の仕入れができるからで、新築特有の「新築プレミアム」と呼ばれる価格の上乗せもありません。
できるだけ参入のハードルを下げる意味で、安くてよいものを仕入れるには中古区分マンションを選ぶのが最も無難です。しかし、ただ中古区分マンションであれば何でもよいわけではありません。重要になるのは付加価値と差別化なので、中古区分マンションに「ひと手間」を加えて付加価値を高める方法について解説します。
2-2.リノベーションで家賃アップも可能
中古区分マンションに加える「ひと手間」としておすすめなのが、リノベーションです。部分的なリフォームではなく、物件全体のコンセプトや世界観を変えてしまうほどのリノベーションをすることにより、中古物件を新築とは異なる価値観で再生することができます。
マンションはそもそも画一的なコンセプトで設計されているため、物件の内部に入るとどこのディベロッパーが建てたマンションなのかわからないことがほとんどです。それだと競合物件との差別化が難しいので、多様化する価値観に応える形でリノベーションをして「他とは違う」空間を求める人に訴求します。
差別化を図ることで価格競争に巻き込まれることもなく、家賃アップを見込むこともできます。
3.中古リノベーション投資が初心者におすすめの理由
中古リノベーション投資はすべての不動産投資家におすすめできる投資ですが、特に初めて物件を購入しようと考えている不動産投資の初心者の方にこそ、中古リノベーション投資が有効であるといえます。その理由はおもに3つあるので、それぞれ1つずつ解説します。
3-1.好立地の物件に安く投資できるためリスクを抑えられる
不動産は読んで字のごとく、動かない(動かせない)資産です。そのため1つとして同じ物件は存在せず、全く同じ設計の建物であっても建っている場所が違えば別物の物件です。
首都圏ではマンション価格が高騰するほどマンション流通市場が活況を呈しており、毎年多くの新築物件が供給されています。株式会社不動産経済研究所のレポートによると、2021年の1年間だけを見ても首都圏では23.5%もの供給増がありました。
しかし、どれだけ新築のマンションが優れたスペックを有しているとしても、すでにマンションが建っている場所に建てるわけにはいきません。後から建てられるマンションほど、マンションを建てる立地条件は狭まっていきます。
中古マンションのなかには、建物が古くなっているものの好立地の物件が少なくありません。その当時はまだまだマンションを建てるのに適した立地条件の土地が多く残されていたことを示しており、こうした好立地物件は建物こそ古くなっているかもしれませんが、立地条件が劣化することはありません。
3-2.リノベーション物件というだけで競合と差別化ができる
マンションの室内デザインには、セオリーのようなものがあります。そのほとんどは画一的で、室内にいるだけだとどこのディベロッパーが建てたマンションなのかわからないほどだというのは、すでに述べたとおりです。マンションの室内デザインには流行のようなものがあるので、同じ時代に建てられたマンションの多くは似通ったコンセプトになっています。
これだと築年数が経ってしまうことで「古い」「流行遅れ」の物件になってしまい、たとえ好立地であっても家賃を引き下げなければ入居者を見つけるのは難しいでしょう。
しかし、現在のリノベーションは施工技術も高くなっており、新築と見違えるほどの品質にまで物件の付加価値を再生することができます。もとより好立地のマンションをリノベーションすれば、「古い」「流行遅れ」の問題を解消して差別化を図り、集客力の高い物件を創りだすことができるわけです。
3-3.時代に合っており受け入れられやすい
マンションを新築するとなると大掛かりなプロジェクトになりますが、リノベーションは1部屋単位で室内空間のリニューアルをすることができるため、小回りが利くこともメリットの1つです。
一度リノベーションをしたら終わりというわけではなく、リノベーション後にまた年数が経過して時代に合わなくなってきていると感じるのであれば、必要に応じてその時代にマッチした物件に作り替えることもできます。
マンション投資には、入居者という「マーケット」が存在します。そのマーケットのニーズに耳を傾けて受け入れられやすい物件を提供することは、これからの不動産投資に求められるスタンスです。
4.不動産投資物件を選ぶ時の注意点
不動産投資のための物件選びには、いくつかの注意点があります。その注意点を個別に解説していきます。
4-1.賃貸需要の見通しを確認する
賃貸の需要がある地域かどうかは、投資物件を選ぶうえで最も重視すべきポイントです。例えば、大都市圏の都心なら多くの企業やさまざまな施設があり働く場所も多いことから人口流入が続いているため、堅調な賃貸需要が期待できます。
一方、地方でもある程度賃貸需要の高い地域はありますが「今後人口が減らないか」などを慎重に判断しなければなりません。
「企業城下町」と呼ばれるような地域で見られる大企業やそれに関連する下請け会社などに依存した賃貸需要なら、経営悪化などによる撤退や縮小のリスクもあります。そうした判断は、十分な投資経験と経済知識が必要なため、初心者は手堅く安定した都心の物件から投資をはじめたほうが安全です。
4-2.ニーズと物件がマッチしているか確認
物件を選ぶときは「地域のニーズにマッチしているか」についてしっかりと確かめてから購入することが大切です。ニーズに合っていない場合は、入居者に選んでもらえず空室となって家賃収入が得られません。そこでニーズをチェックするための基本的なポイントを把握しておきましょう。
-
ワンルームタイプとファミリータイプ
マンションには、単身者用のワンルームタイプと家族が住むためのファミリータイプがあります。物件がある地域がどちらのタイプに需要があるかしっかりと確認しましょう。
都心や大学周辺などワンルームタイプの需要の高い地域もあれば、大企業や住宅地の周辺などファミリータイプの需要が高い地域もあります。まずは、この2つのタイプを確実に見分けるようにしてください。
- 賃貸ではワンルームが有利
ワンルームタイプとファミリータイプのどちらかを選ぶとしたら賃貸ではワンルームがおすすめです。ファミリータイプは、家族で相談したり子どものことを考えたりする可能性も十分あり得るため、空室になったときに次の入居者が決まるまで時間がかかる傾向があります。
その一方でワンルームの場合は、1人で物件を選ぶ傾向があるため、決定するまでが早く空室期間が短くなりやすいのです。またワンルームは面積や設備の規模も小さいため、補修やクリーニング、リノベーションの費用が抑えられるメリットもあります。
そのため空室になりにくく、維持費も抑えやすいワンルームタイプが不動産投資の初心者にはおすすめです。
- 賃家賃重視か利便性重視か
物件のある地域で「家賃と利便性のどちらが重視されるか」についても確かめておきましょう。地方と比べて経済状況が良い都心であれば、家賃よりも利便性を重視して物件を選ぶべきです。
逆に周囲の競合を見て家賃相場が低いようなら手ごろな家賃設定が可能な物件を選びましょう。ただし、家賃は投資において原資回収につながる重要なポイントです。
家賃の安さではなく利便性で物件が選ばれる地域で正当な家賃設定の投資をしたほうが、早めに原資回収ができることは不動産投資の基本となる知識なので押さえておいてください。
- 付加価値のある部屋が求められるか
検討する物件の地域では「付加価値のある部屋が求められるのか」「単に住めれば良いという部屋が求められるのか」なども確かめましょう。
例えば都心は賃貸の需要が高く物件も多いため、単に住めるだけでなく付加価値のある部屋が選ばれやすい傾向です。個性的な内装だったりデザイン性のある設備が付いていたりすると入居者も魅力的に感じるでしょう。
逆に「住めれば良い」という入居者の多い地域では、個性的な物件は敬遠され、どちらかというと家賃が安い物件が好まれる可能性があります。
4-3.周辺環境や利便性もチェック
賃貸の物件選びは「どのような部屋か」だけでなく周辺の環境や利便性も重要です。例えば都心のように主要な移動手段が鉄道なら駅までの距離は大切な条件の一つとなります。
毎日利用する人が多い傾向のため、駅に近いほど入居者が集まりやすくなるでしょう。「〇〇駅まで徒歩何分」という表現をしますが、その数字が1桁ならかなり目を引きます。
さらに食料品や日用品など日常的な買い物をする店舗が近ければより有利です。逆に周囲に音や匂いを出す工場などがある場合は、入居者から敬遠されるため近くに嫌悪施設がないかも確かめましょう。
4-4.任せる管理会社のフォローが重要

初心者が不動産投資を行ううえで物件選びと同様に重視したいのが、物件管理を任せる管理会社です。管理会社選びを失敗してしまうと、物件の対応に手間や時間を取られて副業で投資をする人なら本業に影響を及ぼしかねません。
通常は、物件を購入する不動産会社がそのまま管理を行ったり、紹介されたところへ任せることが一般的です。
- 入居者管理は空室対策で重要
入居者管理とは、以下のような仕事のことです。
- 入居者募集
- 契約の手続き
- 家賃の集金
- 滞納への督促
- 退去する手続き
- 立ち会い
- クレーム対応など
非常に手間がかかる細かな作業がたくさんあります。しかし、きちんと対応してもらわないと入居者が不満を抱き他の物件へ移ってしまいかねません。そのため、物件購入後にどのような入居者管理が行われるかしっかりと説明してもらいましょう。細かい配慮ができる管理委託先を選ぶことが必須です。
- 建物の維持管理は知識が必要
初心者は、値段が手ごろな中古物件から不動産投資をはじめることが多いのではないでしょうか。そこで気をつけたいのが建物の維持管理がどのように行われるかです。
中古物件は、状態によって購入後に補修が必要になることもあります。そのため、もし保証期間が終わっていれば所有者の費用負担で対応することになります。中古物件の場合は、ある程度やむを得ないことかもしれませんが、あまりに多くの費用がかかるとせっかくの家賃収入が削られてしまいかねません。
そこで管理会社による丁寧な建物状態のチェックや先を見越した修繕の提案が大切になってきます。なぜなら、壊れてしまってから修理するよりも点検で傷んでいるところを見つけ先手を打って直したほうが出費を抑えられるからです。
特にキッチンなどの水回りはトラブルになると広い範囲に被害が出てしまいます。物件を選ぶときに傷みなどをしっかりと教えてくれて、可能なら購入にあわせて修繕など手配してくれる管理会社なら安心できるでしょう。
2022年4月からはマンション管理適正評価制度といって第三者機関がマンションの管理状態を評価する制度が運用されます。この制度の運用開始後は管理状態を100点満点の得点で表示されるようになるので、できるだけこの制度を利用して管理状態を公開している物件、そして得点の高い物件を選ぶようにしましょう。
5.不動産投資初心者によくある失敗例と解決策
不動産投資の初心者が陥りやすい失敗には、「ありがちなパターン」があります。そのパターンに陥ってしまうことがないよう、5つの失敗パターンとそれを回避するための解決策を解説します。
5-1.十分な資金なしに始めようとする
不動産投資に限ったことではありませんが、投資は資金管理がとても重要です。不動産投資では金融機関の融資を利用することができるため、物件購入に必要な資金の一部を用意すれば始められるメリットがありますが、だからといって資金が十分ではない状態から始めるのはリスクが高すぎます。
想定外の空室や修繕などが発生して資金ショートしてしまうと、最悪の場合は物件を手放して借金だけが残ることにもなりかねません。
【解決策】
十分な資金で臨むことは不動産だけでなくあらゆる投資、事業の鉄則です。予想外の事態になっても資金に余裕をもっておけば慌てずに済みますし、「途中退場」を避けて継続することで、長期目線でトータル収支をプラスにもっていく不動産投資本来の実力も発揮できます。
フルローンといって自己資金ゼロで始めることも不可能ではありませんが、だからといって本当に資金ゼロで始めた場合、わずかな計算違いが起きただけでも危機的状況になるのは容易に想像がつくと思います。
5-2.営業トークを鵜呑みにしてしまう
不動産投資の初心者にとって、不動産会社の担当者は最も身近なところにいる不動産のプロです。そのプロが勧めている物件なのだから買っても問題ないと思いたいところですが、それは早計です。
不動産会社の方針やモラルによる部分があるため、その物件が本当に「買うべき物件」なのか、それとも「売りたい物件」なのかはわかりません。後者の物件を掴んでしまうと空室に悩まされて期待どおりの収益が上がらず、ローン返済の「持ち出し」に苦しめられることもあります。
【解決策】
投資の基本は自己判断、自己責任です。提案を受けることは構いませんが、決めるのは自分自身です。営業トークだけを情報源にするのではなく、自分でも勉強してその提案どおりになるのかどうかを自分で精査する「目」を養いましょう。それで腑に落ちない部分がある物件は、買うべきではありません。
5-3.新築のワンルームマンションを購入してしまう
不動産投資初心者に新築ワンルームマンションを推奨する不動産会社やネット記事などをよく見かけますが、新築ワンルームマンションはキャッシュフローが赤字であることが前提になっていることが多く、入居者が付いているのにローン返済のために「持ち出し」を余儀なくされることも多くあります。
ではなぜ新築ワンルームマンションを買う人がいるのかというと、「資産形成のため」「節税できる」という営業トークがあるからです。ローン返済中は「持ち出し」があったとしても「節税になる」と勧めたり、完済後はキャッシュフローが黒字になって将来の収入源になるといわれたりしますが、ローンを完済した20年後、30年後にその物件が新築時と同じ価値を保っているとは考えにくく、家賃の引き下げや空室率の上昇によって収益性が低下する恐れがあります。
【解決策】
マンション価格が高騰している昨今、ワンルームマンションに限らず新築は高い物件が多いため、収益性を高めることは難しいのが実情です。「新築プレミアム」が上乗せされているせいで、取得価格が高くなると利回りの低下を招き、赤字となることも珍しくありません。
最初から節税が目的である、赤字であっても十分な資金力があるといった場合は別ですが、不動産投資初心者こそ値ごろ感のある中古物件から始めることをおすすめします。
5-4.家族に内緒で始めてしまう
不動産は高い買い物なので、「借金をしてまで買う」ことに家族から反対されることを懸念し、家族には内緒にしたままで、自分の判断だけで物件を購入するといった事例があります。
本人に安定的な収入があればローンの審査にも通る可能性が高いので、家族に内緒で始めることは不可能ではありませんが、少しでも思惑が外れるような事態が起きたときには金銭面だけでなく、家族からの信用面でのリスクが顕在化します。
「勝手に始めた不動産投資」が原因で離婚に発展したり、家族の信頼関係に重大な影響を及ぼしてしまうことは、決して他人事ではありません。
【解決策】
不動産投資は自分だけでできるものではなく、配偶者や家族の理解があってはじめて成立するものです。反対されたのであれば十分な説得材料や資金を用意してから再び同意を求めるなど、「反対する側にも一理ある」という考えをもって家族との信頼関係を大切にしましょう。
5-5.不動産投資のリスクを理解せず始めてしまう
投資である以上、不動産投資にはさまざまなリスクがあります。空室や滞納、家賃低下、災害や火災による損壊、金利上昇などのリスクはいずれも投資家が知っておくべきもので、これらのリスクが現実になったとき、投資を継続できるだけの態勢を整えておかなければ、「途中退場」になってしまって物件を手放し、借金だけが残る事態もあり得ます。
【解決策】
不動産投資にリスクは付き物です。考えられるリスクが現実になっても致命傷にならないような資金計画やリスクヘッジをしたうえで臨むのが不動産投資なので、それができていないうちはそもそも不動産投資を始めるべきではありません。
6.不動産会社選びが最も重要
不動産投資の物件選びで最も大切なのは、物件を購入するときの不動産会社です。なぜなら「ニーズと物件がマッチしているか」「賃貸需要の見通し」「周辺環境や利便性」などは、初心者が自分で確かめることが非常に難しいからです。
そのため、さまざまな情報を丁寧にアドバイスしてくれる不動産会社と出会えるかどうかが初心者にとって安心して物件を選ぶための最重要ポイントになります。
あわせて物件管理も行っている不動産会社なら別に管理会社を検討する必要もありません。これから解説する点に注意しながら最適な不動産会社を選ぶようにしましょう。
6-1.収支計画を立ててもらう
初心者は、物件の条件や状態に目が向きがちですが、忘れてはいけないのが収支計画です。収支計画とは「所有してからどのくらいの家賃収入が見込めるのか」「どのような出費が予想されるか」など見通しを立てることで、不動産投資を成功させるためにはとても重要な作業です。
物件を選ぶときは不動産会社にこの収支計画をしっかりと作ってもらい、納得できる提案をしてくれた会社を選ぶようにしましょう。
6-2.良い不動産会社の特徴
不動産投資の成否は選ぶ不動産会社によって変わるといえますが、それでは良い不動産会社には何が必要なのでしょうか。以下の5項目を判断材料として精査してください。
- 物件の事情を理解している
提案している物件について十分に理解をしていて、メリットだけでなくデメリットなど都合の悪いことまで熟知したうえで提案しているかどうかは、リスク管理の観点からとても重要です。
- 物件周辺に土地勘があり現地を見て紹介している
不動産は動かない資産だけに立地条件が価値を決めるといっても過言ではありません。物件そのものだけでなく周辺環境や利便性などの土地勘があって、それを踏まえた提案をしているかどうかも「購入後の未来」をイメージするために必要です。
- リスクについてもきちんと説明してくれる
提案している物件の良いところを伝えるのは簡単ですが、本当に必要なのはリスクの説明です。どんなリスクがあるのか、そのリスクが現実になると何が起きるのか、そのリスクを適切に管理するにはどうすれば良いのか。この3点が揃った説明になっているかどうかを精査しましょう。
- 購入後も賃貸管理を行ってくれる
不動産投資は物件を購入したら終了ではなく、そこからがスタートです。適切に物件を管理していくことも収益を確保するうえで欠かせない「業務」です。投資家目線で営業活動をしている不動産会社は購入後の管理も含めた提案やサービスの提供をしているので、「購入後のサービス内容」もチェック項目に加えておきましょう。
- 金融機関との信頼関係を築けている
ほとんどの場合、物件購入のために金融機関のローンを利用することになります。不動産の購入だからといって簡単に審査に合格できるわけではなく、収益性や購入者本人の属性などが入念に審査されます。
それに加えて重要なのが、不動産会社と金融機関の信頼関係です。金融機関は物件を販売する不動産会社の信頼度も審査しているので、紹介できる金融機関が充実していること、それらの金融機関との信頼関係がしっかりと築けていることも不動産会社の「品質」に直結します。
6-3.セミナーや勉強会に参加してみる
不動産会社が主催するセミナーや勉強会へ参加することも不動産会社を選ぶうえでとても役立ちます。担当者と実際に会って話を聞くと対応の丁寧さや仕事へ取り組む姿勢などが分かるため、任せるかどうかの大きな判断材料になるでしょう。さらに最新の物件情報やネットには流れない現場のリアルなノウハウを知ることができるかもしれません。
投資家として今後のレベルアップにも役立つため、一度気になる不動産会社のセミナーや勉強会に参加してみることをおすすめします。
- セミナーの選び方
当記事では中古区分マンションをリノベーションして付加価値を高める投資方法を紹介しました。類似物件との価格競争に巻き込まれることなく安定的な賃貸経営をするには差別化がとても重要なので、リノベーションを活用した不動産投資に注目してみることをおすすめします。
初心者向けの「リノベーション投資」を丁寧に解説するセミナーも開催されているので、こちらもぜひ参考にしてください。
7.初心者こそ信頼できる不動産会社をしっかりと選ぼう
不動産投資の初心者は、不動産のプロではありません。だからこそ不動産会社の役割はとても大きく、信頼できる不動産会社をパートナーにすることができれば不動産投資は成功できる確率がとても高くなります。
不動産投資についての勉強と同時に、信頼できる不動産会社との出会いも大切にしてください。