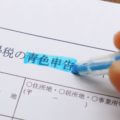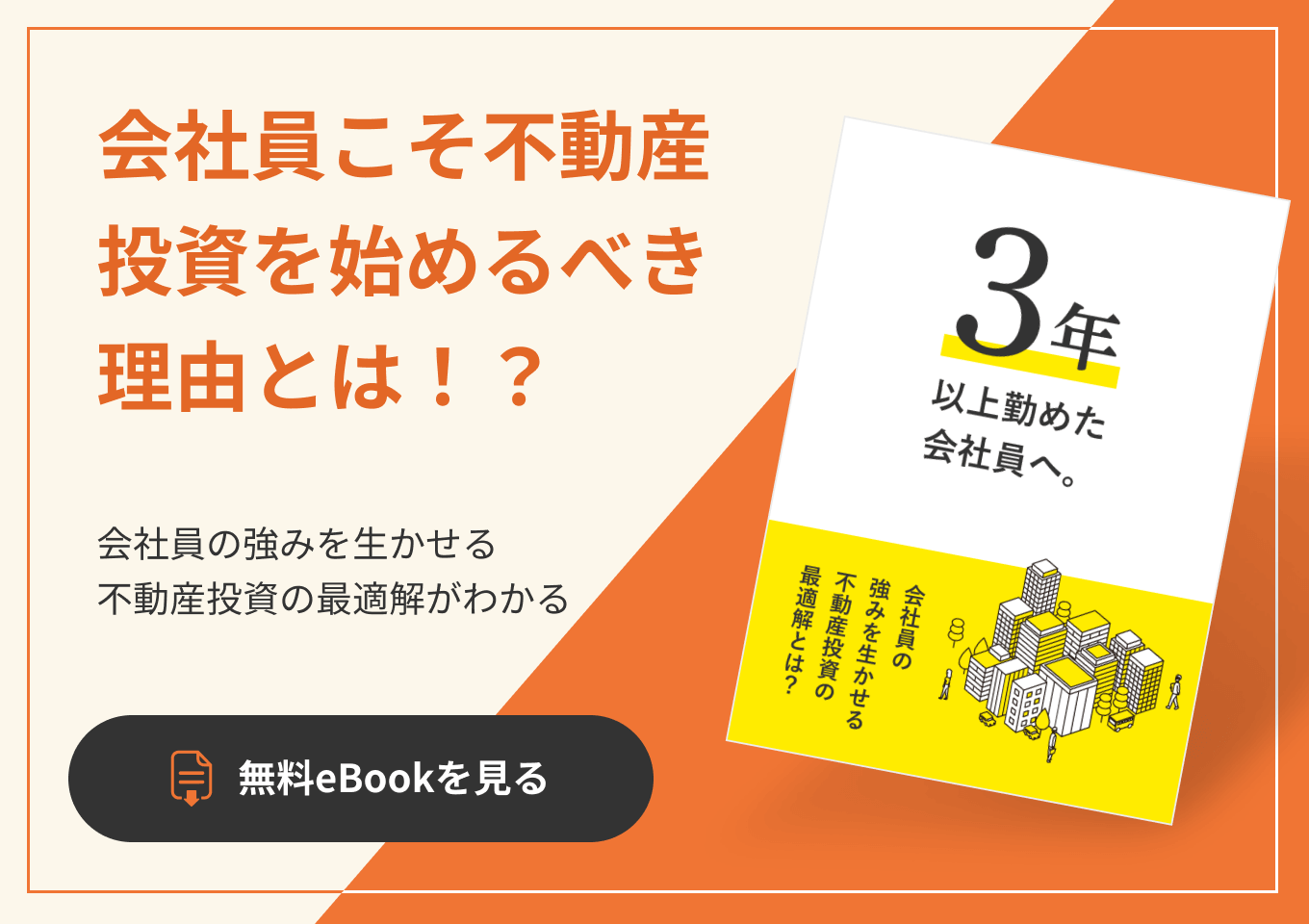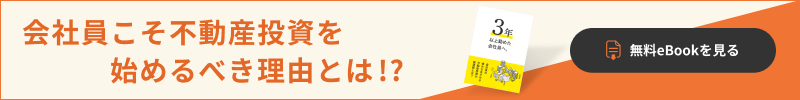不動産投資にかかる税金と所得税の仕組みを理解しよう
長期にわたって家賃収入を得る不動産投資では、毎年上手に節税して十分なキャッシュフローを確保しながら運用していくことが重要なテーマとなります。そこで今回は、不動産投資を始めたい人が知っておきたい不動産投資にかかる税金と所得税の仕組みについて解説します。

所得税の仕組みと確定申告の仕方
所得税は、個人が得た所得の合計に応じた税率を乗じて計算されます。不動産投資を行っている場合は、家賃や礼金などの収入からローン金利や修繕費用、賃貸管理委託料などの経費を差し引いた金額が所得となります。
日本では所得が多くなれば多くなるほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されており、所得税率は5%(年間所得195万円以下)~45%(年間所得4,500万円超)の7段階まで設定されています。(2020年時点)そのため会社から給与を受け取っている人が不動産投資を始めると、給与所得に不動産所得が加算され所得税率の区分が上がってしまう可能性があるので注意が必要です。
確定申告は、申告対象年の翌年2月16日~3月15日の間に行います。ビジネスパーソンの場合、会社から年末に源泉徴収票が配られた後、それをもとに確定申告書を作成するのが一般的です。給与所得は企業側で各種控除などを計算してくれますが、不動産所得は収入と経費を自分で計算するか、税理士に依頼して計算してもらう必要があります。
また申告する際は「税務署の窓口」「税務署へ郵送」「e-Taxで電子申告」といった方法から選択することができます。1回だけの申告であれば税務署の窓口で申告手続きをする方法でもいいのですが、不動産投資の場合は毎年確定申告をする必要があるため、e-Taxで電子申告ができるようにしておくと後々便利でしょう。
不動産投資で節税ができる理由
不動産が節税になるといわれている理由は、所得の「損益通算」ができるからです。例えば、ある年の給与所得が900万円で不動産所得がマイナス100万円だったとします。年度内に大規模なリフォームを施して経費として計上した場合は、不動産投資では不動産所得が赤字になることも珍しくありません。この場合、その年の所得税の損益通算を行います。
給与所得の900万円から不動産所得のマイナス100万円を引いて総所得を800万円とし、所得税を計算します。損益通算して確定申告を行えば、給与所得900万円を前提に源泉徴収で納付していた所得税の一部が還付されるのです。また相続対策として節税を考えるうえでも不動産投資は有効といえるでしょう。なぜなら現金で相続した場合は額面通りの相続税評価額になってしまうからです。
しかし不動産の場合は市場価値よりも評価額が大きく下回ります。相続税は「資産の評価額×税率」で決定するため、資産の評価額が下がれば相続税も少なくなるというわけです。もちろん相続税が下がったからといって市場価値が下がるわけではありません。

所得税以外の注意するべき税金
不動産投資では所得税以外にも税金が発生します。これらの取り扱いに注意しながら収益不動産を上手に運用していきましょう。ここでは「固定資産税」「不動産取得税」「住民税」について解説します。
- 固定資産税
固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有していると毎年発生する税金です。言い換えると不動産投資を行う場合は、毎年必ず支払う必要がある税金になります。納税額は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額である「課税標準」に、標準税率または各市町村(東京都23区は都)が定める税率を乗じて算出されます。地域や築年数、建物の構造などによって額は変わってきますが、戸建ての場合は10万円~12万円程度、マンションの場合は8万円~10万円程度となることが多いようです。なお、固定資産税には税額が調整される特例がいくつかあるため、固定資産税を念頭に投資として魅力的な物件かどうかを判断することも一つの基準となるでしょう。
- 不動産取得税
不動産を購入した後に課税される税金で、納税するのは購入後の1回のみです。例えば家賃10万円のワンルームマンションの購入に60万円の不動産取得税が課税されれば半年分の家賃収入に相当します。不動産を取得してから不動産取得税の通知が来るまでにはタイムラグがあるため、うっかり忘れていると収支計画が合わなくなる場合もあるため注意しましょう。
- 住民税
当該年度の所得によって翌年の住民税が変動する仕組みです。不動産投資で所得が増えたとしても、翌年の住民税がそれに合わせて増税されることを忘れないようにしましょう。不動産投資などの資産運用の経験がないビジネスパーソンは、勤務先が所得税を源泉徴収し年末調整まで行ってくれるため、所得税や確定申告について考える機会は少ないでしょう。しかし、自身で不動産投資を始める場合、これまで通り人任せにというわけにはいきません。
事前に知識をつけておくことは、手元に残るキャッシュを増やすことにもつながります。税金に関する最低限の知識は身につけたうえで、不動産投資に挑むようにしましょう。