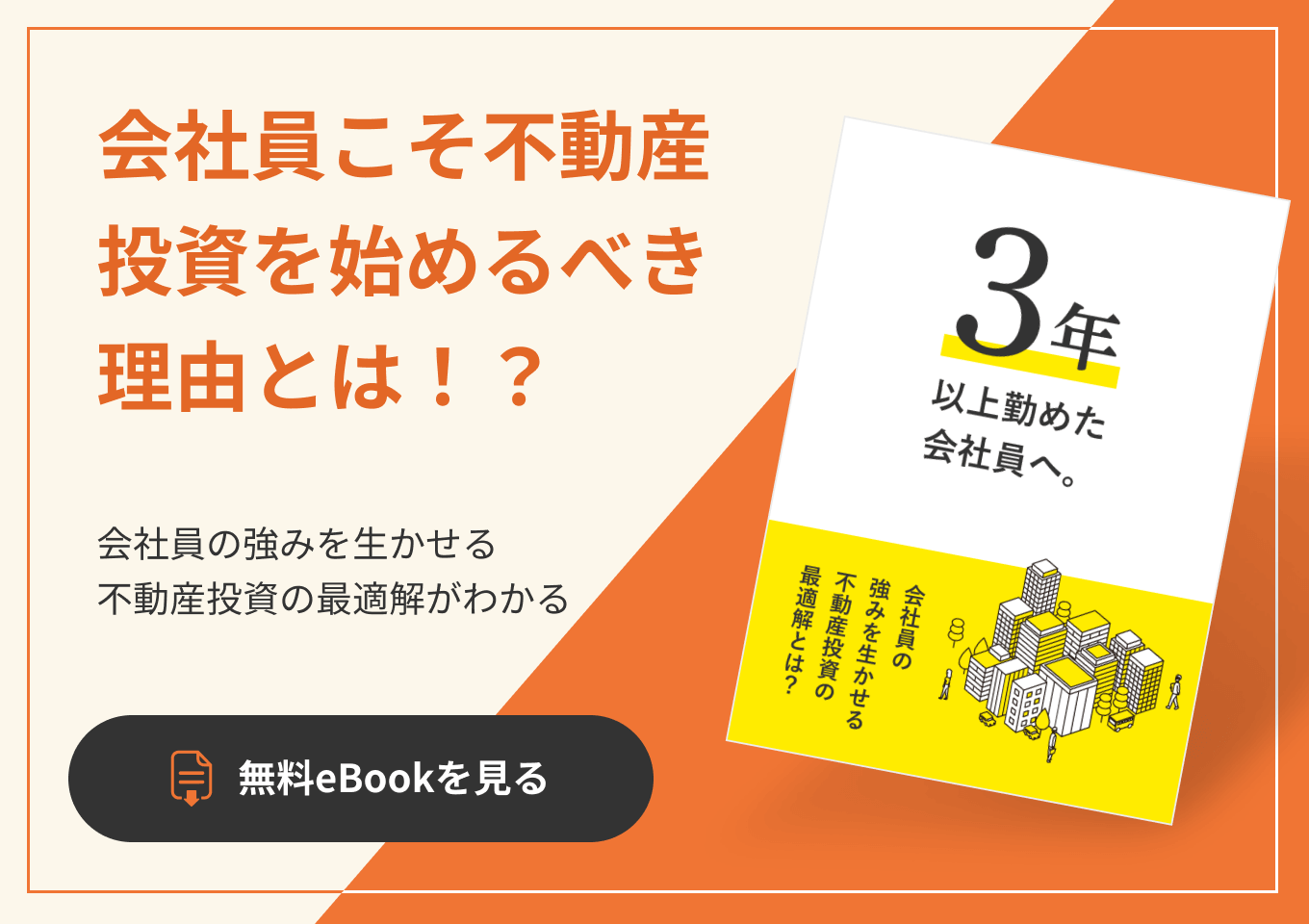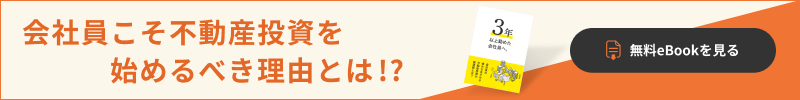ワンルームマンション投資は危険って本当?物件選びの正解5大法則
不動産投資に興味を持ち、少し調べていくと「ワンルームマンションの投資は危険だ」という内容の記事や検索語を見かけることがあります。不動産投資は事業であり、大きな資金を投資しますので、事前の準備が不十分であれば危険な目にあう可能性があります。
しかし、十分な下準備と勉強を重ね、慎重に物件を選んでいけば、他の投資方法よりも比較的、安全で成功しやすい投資方法と言えます。そのため、多くのサラリーマンが、将来の年金サポートや、FIREの準備としてワンルームマンションの不動産投資を検討しています。
本記事では、不動産投資のひとつである、ワンルームマンションへの投資についてまとめています。

目次
1.ワンルームマンション投資とは
ワンルームマンション投資とは、ワンルームマンションを人に貸す目的で購入し、その部屋を賃貸に出して、賃料収入を得ることを目的にした不動産投資方法です。
アパート一棟やマンション一棟などを所有して行う不動産投資は莫大な初期費用がかかりますが、ワンルームマンション投資は一区画のみを所有するスタイルのため、はじめて不動産投資をする方にも、比較的ハードルが低い投資方法です。
ワンルームマンション投資に使う物件は、事業用の不動産として、金融機関から融資を受けて購入します。ローンは入居者からの賃料で支払っていきますので、オーナーとなる方は最小限の投資資金で不動産投資をスタートでき、最終的にワンルームマンションを所有することができます。
ローン完済後は、賃料収入から経費を差し引いた金額が全額、オーナーの収入となります。不動産投資を始めている方の多くは、このように、将来的にご自分が希望する金額を長期安定的に得る方法のひとつとして、ワンルームマンション投資を選んでいます。
2.ワンルームマンションと他の不動産との違い4つ
本章ではなぜ、ネット上で「ワンルームマンション投資が危険」だと言われているのかを、他の不動産投資方法と比較しながら、やさしくまとめています。
結論から言えば、このような検索語や記事は、ワンルームマンション投資を含んだ、不動産投資全体への理解が不十分なことが原因である傾向にあります。以下は、ネット上で、ワンルームマンション投資が危険だと言われている主な理由です。
2-1.入居期間が短い
ワンルームマンション投資は、基本的に単身者を対象としているため、主な入居者は学生または独身の社会人です。学生は卒業のタイミングで退去することが多く、独身の社会人も転職などのタイミングで数年の間に引っ越しをする可能性が高くなります。
このようなことから、ワンルームマンションは入居期間が短く、長期安定経営がしにくいため、危険であると言われている傾向にあります。しかし、同じ不動産投資の単身向けの木造アパート経営でも、学生の卒業とともに人は入れ替わりますし、ファミリー向け物件であっても、転勤による引っ越しは会社員であればつきものです。
そのため、入居期間がある程度限定されていることは、賃貸物件であれば当たり前のことであり、特にワンルームマンションに限ったことではありません。
むしろ、駅前にある通勤通学に便利で、設備の整ったワンルームマンションであれば、他の物件よりも入居者は決まりやすく、一定のタイミングで新規入居者が入れ替わる、回転効率の良い賃貸経営が期待できます。
2-2.キャッシュフローが少なめ
不動産投資におけるキャッシュフローとは、不動産収入から経費を差し引いた手残りの金額のことです。ローン返済中はローン返済月額と運営経費、ローン完済後は運営経費が賃料から差し引かれます。
ワンルームマンションの賃料は、一般的な不動産の賃料と比較すると高くはないことから、経費を差し引くと、手残りの金額が少ないことが危険視されています。
しかし、不動産投資をワンルームマンションではじめる方の多くは、将来的に「プラスアルファ」の収入が欲しいという未来図を描いてスタートしています。例えば、老後年金にプラスアルファ、毎日の生活費としてプラスアルファなどと考えています。
このように、もともと不動産投資による収入に大きな金額を期待していないため、1室からのキャッシュフローが少ないことは、ワンルームマンション投資を選択する方にとっては想定内であり、さほど危険と感じる要素にはなりにくい傾向にあります。
むしろ、将来的に大きなキャッシュフローを得るために、大型物件を購入して莫大な融資を受けることのほうが危険だと感じているからこそ、はじめやすい価格からスタートできる、ワンルームマンション投資を選択しています。
また、将来的に手残りの金額をもっと増やしたいと思った場合は、ワンルームマンション投資であれば、追加で所有区分を増やしながら、自分にできる範囲で、希望する金額にまで時間をかけて到達できるため、より安全で、より確実な資産形成法だと言えます。
2-3.節税効果が意外と薄いから
不動産投資には、所得税と相続税への節税効果があります。相続税は相続が起きない限りは発生しませんが、所得税は毎年必ず発生する税金ですので、節税対策としてワンルームマンション投資を検討する方もいます。
節税方法は主に、マンション投資にかかった費用を経費として計上し、所得税の課税対象額を減らして、所得税率の引き下げを狙います。特に、年収が1,000万円を超える方は、所得税率が高く、毎年多額の所得税が発生していますので、マンション投資による節税効果は大きいと言えます。
また、サラリーマンの場合は、「損益通算」という方法で節税が期待できます。不動産投資の経費が不動産収入を上回れば不動産所得は赤字になりますが、損益通算をして、サラリーマンの給与収入に不動産投資の赤字をぶつけることができるため、所得税と住民税の課税対象金額を下げることができます。
特に、不動産投資物件を購入した年は、物件購入の手数料・税金などを支払って経費がたくさんかかるため、ほとんどのケースで赤字となります。その結果、サラリーマンとして給与から源泉徴収された分が還付されるので、「儲からなかったけど、節税はできた」という状態になります。
ワンルームマンション投資の事業者の立場として考えれば、マンション購入費はかかったけれども、その年は所得税の支払いがなく、還付金まで戻ったのであれば、文句のつけようがない年度だったと言えるでしょう。
このような経緯が、いつしか「不動産投資をすると節税ができる」というイメージにつながり、節税効果が少ないワンルームマンションの不動産投資は危ない!という考え方につながっている可能性があります。
しかし、そもそも、本来の不動産投資の目的は、長期安定した家賃収入を得ることです。そのため、損益通算で節税することを主な目的に、ローンを組んで不動産投資をするのであれば、どんな不動産投資でも危険です。
また、不動産投資による節税メリットは、初年度と大きな経費計上ができる減価償却費がある間は続きますが、減価償却は年々減っていき、いつかは黒字経営となり税金を支払うことになります。
節税ができることは、あくまで不動産投資をするメリットの一つであり、目的ではありません。節税効果が薄いからワンルームマンション投資が危険だという考えは、不動産投資全体を十分に理解していない状態だと言えます。
2-4.売却方法が限られてくるから
不動産投資には投資期間全体で、最終的にどのようにして利益を確定するかを計画しておく、「出口戦略」という考え方があります。一般的には、不動産の値段が上がった時に売却をして、トータルの収支を黒字にする方法を取ります(もちろんずっと所有していても問題ありません)。
ワンルームマンション投資が危険だと言われる理由には、ワンルームマンションが売りにくく、出口戦略に失敗しやすいという考え方があるためです。なぜ失敗しやすいかというと、不動産市場における不動産購入希望者の多くはマイホーム購入を希望しているため、市場全体の中ではワンルームマンション購入希望者は、少数派となるからです。
その結果、中古ワンルームマンションの主な買い手は不動産投資家ということになります。しかし、不動産投資家にもプロから初心者までさまざまな方がいらっしゃいます。中古になって手ごろな値段になったワンルームマンションは、不動産投資初心者が手を出しやすい、手ごろな値段設定であることが多く、決して、買い手が見つからないタイプの物件ではありません。
つまり、はじめから不動産投資家を対象に売りに出せば、買い手が見つかりやすいのです。このようなことから、一般に言われている「ワンルームは買い手がつかないから危険だ」という考えは、やはり、不動産投資全体への理解が浅い状態であると言えます。
以上のことから、ワンルームマンションへの投資は、決して危険なことではなく、不動産投資に関する情報をしっかりと集め、内容を理解していけば、決して無理な投資方法ではないことがわかります。
次章からは、ワンルームの中でも新築と中古で、どのような違いがあるのかも見てみましょう。
3.ワンルームマンション投資が危険と言われる3大理由 新築編
本章では新築のワンルームマンションに限定した、ワンルームマンション投資が危険となる要因を3つにまとめています。
3-1.価格が高い
不動産全体に言えることですが、新築物件というのは、価格が最も高い状態です。そして、不動産は新築の翌年から「中古」になり、値段が下がります。
不動産投資では物件購入のために銀行から融資を受けますので、新築で買うと借入額も大きくなります。ただし、新築物件は入居者も付きやすく、設備も最新ですので、不動産としての価値が高く、銀行融資も比較的スムーズです。また、周辺相場よりも高めの賃料設定でも、入居者が決まりやすいという特徴があります。
物件の立地条件が良く、空室もない経営ができれば、新築ワンルームマンションで投資をしても問題は起きにくく、危険なことはありません。
しかし、新築は物件購入価格が高いため、ワンルームマンション投資であっても高額のローン返済額になりやすく、空室が続くとローン返済を持ち出しで支払うことになる可能性が高いため注意が必要です。
3-2.家賃を下げることになりやすい
一般的にワンルームマンションは、通勤通学に便利な駅近に建てられます。そのため、せっかく新築のワンルームマンションを購入しても、すぐ近くに同じような新築のワンルームマンションが建っていくことになります。
ワンルームマンションは部屋の広さや設備においても差別化が図りにくいため、どうしても新しいもののほうが物件としてのスペックが良くなります。
このようなことから、新築のワンルームマンションは競合が多くなりやすく、ライバル物件との差別化や空室リスク回避のために、将来的に賃料を下げて対抗しなければならない確率が高くなります。
そのため、当初の計画よりもかなり早い段階で、賃料を下げないと、返済計画に問題が生じやすくなる可能性があります。
3-3.高くは売れない
新築で買ったワンルームマンションは、すぐに中古扱いになりますので、基本的に買った時と同じ値段以上で売れることはありません。
立地条件や設備が良い・築年が浅いなどの好条件が揃っていれば買い手は早く見つかりやすいですが、あくまで中古市場での相場価格の範囲内です。
以下のグラフは、レインズトピックから不動産価格の下落率をまとめたものです。築5年以上の物件は新築時より13%下がり、その後も5年ごとに下がり続けることがわかります。

このような不動産流通全体のトレンドからすると、新築で買ったワンルームマンションが購入時の値段を超えることは、よほどの好景気が来ない限り、かなり考えにくいと言えます。
上記データは平均的な下落率であり、新築時のマンション価格によってはより大きく下落することもあるため、売却による出口戦略で収支を調整する方法は、失敗しやすくなる可能性が高くなります。
4.ワンルームマンション投資が危険と言われる3大理由 中古編
本章では、ワンルームマンション投資が危険と言われている理由を、中古物件に限定して、まとめています。
4-1.修繕費がかかる
ワンルームマンションに限らず、不動産は経年をすると修繕が必要な箇所が増えていきます。国税庁の法定耐用年数表を参照するとわかりますが、マンションの給湯やガスなどに関わる設備類は5~15年の間に徐々に劣化していきます。
経年が進むほど徐々にメンテナンスの間隔は短くなり、修繕費は高くなる傾向にあります。年間の修繕費があまりにも多いと、経費がかさんでしまいキャッシュフローが少なくなることもあります。
建物に付随する修理修繕は物件所有者であるオーナーの義務ですので、入居者確保のためには入退去のタイミングで、問題がなくてもメンテナンスをして良好な状態を維持させていくことで、先々の修繕費負担を減らすことができます。
4-2.空室率が高め
前項で解説したとおり、マンションの築年がすすむと、建物と設備の経年劣化も進みます。ワンルームマンションは駅前などの便利なエリアに集中的に建っていることが多いため、入居者からすると、どれを選んでも立地的には大差がありません。
そのため、似たような間取りと便利さであれば、より設備が良く快適に暮らせる新築や築浅物件を選ぶことになりますので、同じエリアにある中古のマンションは空室率が上がる可能性が高くなります。
空室リスクを避けるためには、値段を下げて対応する必要があるため、賃料下落につながります。周辺のライバル物件の状況によっては、リフォームなどをして対応するなど、経営の見直しの必要性が高くなります。
4-3.売却しにくい
不動産市場の中で、多くの不動産購入希望者はマイホームを探していますので、中古ワンルームマンションは、不動産投資家をターゲットに売却することになります。
しかし、中古物件は修繕費などの経費がかかるため、投資効率が悪いと判断されることがあります。物件によほどの魅力がないと、売却が難しくなる可能性が高いと言えます。
将来の出口戦略として売却も視野に入れている場合は、古くなっても入居者が付きやすい物件を選び、こまめな手入れをして室内の経年劣化をなるべく防ぐような経営努力が必要です。
5.危険ではないワンルームマンション投資の5大法則
本章では、安全で成功しやすい、ワンルームマンション投資の法則を5つにまとめています。
5-1.都心部にある物件を選ぶ
安定してワンルームマンションで不動産経営を行い、将来の「プラスアルファ」の収入を実現するためには、長期的に継続して賃貸需要がある立地選びが大切です。例えば、都心部の駅から徒歩10~15分以内にある、通勤通学に便利で生活にも便利な場所などです。
こういった立地は、その利便性の高さゆえに、常に多くの入居希望者が集まりますので、空室リスクも低く、安定経営をしやすいと言えます。また、都心部は他のエリアと比べて圧倒的に人口が多いため、入居希望者のすそ野も広い点がメリットです。
賃貸物件の中でも、特にワンルームマンションは将来的にオーナー自身が住む可能性が低いため、首都圏にいなくても、東京23区のワンルームマンション経営をすることも可能です。
5-2.ワンルームを選ぶ
都心部で駅に近い便利なエリアには、ワンルームマンションが多い傾向にあります。そのため、不動産経営をしやすい立地条件を最優先にして物件を選ぶと、必然的に、購入すべき物件の候補は、ワンルームマンションに絞られてきます。
ワンルームマンションは、広さや間取りも似ているものが多く、価格帯も手ごろであるため、立地条件の良い物件に絞っていけば、はじめての不動産投資でも、比較的、良質な物件を探すことができます。
どの物件にすればよいのかを決めきれない場合は、不動産会社のセミナーや、相談会などに積極的に参加していくことで、物件を絞り込んでいけるようになります。また、ワンルームマンションの不動産投資に信頼と実績のある、不動産会社とのパートナーシップも、不動産投資で望む結果を出すためには重要です。
5-3.中古物件から選ぶ
新築も中古も、それぞれ良い部分があるのですが、長期的に安定した収入を得るという不動産投資の本来の目的を果たすのであれば、中古のほうがより不動産投資には適しています。
一般的に、新築物件には「新築プレミアム」と呼ばれる、誰も使っていない新しいもの=良いものであり、購入した人に高い満足感と優越感を与えるという価値観があります。このプレミア感によって、相場よりも高い値段がついていても、多くの方が購入していきます。
このような特別な価値観は、洋服・車・スマホ・家電などの、市場にあるあらゆる商品にありますので、当然、ワンルームマンションの価格設定にも反映されます。つまり、新築のワンルームマンションは、実際の価値よりも、高い値段設定であることが多いのです。
しかし、中古のワンルームマンションは実勢価格でのみのやり取りになりますので、プレミアによる余分な価格が内包されていません。また、新築ワンルームマンションであっても、購入後は中古物件になりますので、短期間で市場原理に沿った価格に修正されていくことになります。
物件選びの際にも、その年度の新築ワンルームマンションの竣工件数は限られていますが、中古ワンルームマンションにはその何倍もの選択肢があるため、より土地とエリア条件の良い、経営のしやすい物件から選ぶことができます。
新築のワンルームマンションは、ご自身で住むことを前提に自己満足としてプレミア感を楽しむのであれば問題ありません。しかし、不動産投資としてビジネス目的で購入するのであれば、実際の物件価値に見合った金額である、中古ワンルームマンションが適しています。
5-4.フルリノベ―ションをかける
ワンルームマンションだけに限らず、不動産投資とその後の経営の成功率を高くする方法として、中古物件にフルリノベーションをかけるという方法があります。
フルリノベーションとは、マンション室内を全て取り壊してスケルトン(枠組みだけの状態)にしたうえで、配管・配線・間取りなどの全てを作り直すことです。この方法により、マンションの建物自体は経年をしていても、室内は新品同様にすることができます。
東京カンテイの調査データによると、2022年度の新築マンションの平均価格は6,341万円、中古マンションの平均価格は4,087万円と、購入費には約40%もの値段の開きがあります。仮に、この値段で中古のマンションを購入し、フルリノベーションに1,000万円かかったとしても、新築マンションを購入するよりも1,000万円近く購入費を抑えることができる計算になります。
入居希望者からすると、フルリノベーションのかかった新品同様の部屋なのに、新築物件よりはリーズナブルな家賃で住むことができるためお得感もあります。そして、このような賃貸物件はすぐに入居者が決まる傾向があります。
また、膨大な数の中古物件の中から、不動産経営のために吟味された物件は、エリア条件が良くて住み心地が良いため、長期の契約更新につながりやすく、安定収入にもなりやすい点もメリットです。
このように、フルリノベーションありきでワンルームマンションの不動産投資を考えると、選択肢の幅は無限に広がります。
5-5.正しい物件選びをサポートできる不動産会社を探す
新築・中古に関わらず、不動産経営で成功するために、最も重要なのは物件選びです。しかし、はじめての不動産投資では、不動産投資のプロと同じ市場で、迅速に良質な物件探しをしなければなりません。
投資用不動産の取り扱いがある不動産会社は数多くありますが、正しい物件選びのサポートができる会社は、実はそう多くはありません。
不動産投資に向いた物件の条件は、都心の駅近で便利なところと決まっていますが、実際に物件を探し始めると、ほとんどの方は、その数の多さに圧倒されます。都内23区のワンルームだけに絞っても、選びきることができないほどの物件数があるため、いくつか良さそうだと思えるものをピックアップしても
「本当にこの物件で良いの?」
「ここ、誰か住んでくれるの?」
という不安が常につきまといます。
こうなってしまうことの理由として、市場に出ている多くの物件は、なるべくお金をかけずにローコストで修繕をしていることが多く、結果的にどれも似通ったものになっていることが挙げられます。
汎用性が高いとも言えますが、別の言い方をすれば「誰かが住んでくれればいいや」というタイプの物件でもあるため、ご自分が入居希望者になった立場で考えたときに、選ぶ決め手に欠けていると感じてしまうでしょう。
私たちREISMが手掛けている、中古ワンルームのリノベーション物件は、ライフスタイルにこだわりのある方から、強く支持されています。一般的にリノベーションは、水回りや壁紙を取り換えるなどの修繕を指すことが多いですが、REISMのリノベーションは、「中古物件に新しい価値を付加する」ことを着地点にしています。
具体的には、フルスケルトンのフルリノベーションで配管から完全にやり直します。フローリングには無垢材を使い、経年しても部屋の雰囲気が壊れないような「ロングライフ」の物件に成長することを前提に設計をしています。
これによって、経年しても劣化とはならず、ヨーロッパのアパルトマンのような雰囲気と趣のある、時間経過とともに価値の上がる物件にすることができます。
また、そこに住む人が求める「自分らしさ」を賃貸住宅の中で表現できるように、いくつものライフスタイルを反映したデザインを用意し、ワンルームという限られた間取りの中で、長く暮らしやすい部屋づくりを得意としています。
賃貸であってもマイホームのように、自分らしい暮らし方ができる物件は、探してみるとわかりますが、かなり希少な物件です。だからこそ、入居希望者からすると「やっとみつけた!」と思える価値の高い部屋となり、長く住んでいたい生活満足度の高い物件になり得るのです。実際にREISMの物件を見ていただければ、感覚的な部分でもご納得いただけると思います。
ワンルームマンションでの投資をご検討の際には、REISMの不動産投資セミナーをご活用ください。
6.まとめ
ネットの検索語で見かける、ワンルームマンションの投資が危険だと言われている理由を、さまざまな角度から検証してみました。
一つひとつひも解いていくと、ワンルームマンションだから危険だということではなく、不動産投資全体に対する理解が不十分な状態で、不安に思っているからこそ「危険なのではないか」と感じてしまう内容であることがわかりましたね。
また、具体的な成功ノウハウとして、不動産投資という事業であることを考えると、中古の物件を購入するほうが、実勢価格と物件価値に釣り合ったものを探し出せることも、ご理解いただけたと思います。
さらに、センスの良いリノベーションをかけることで、入居者の満足度が高い賃貸経営をすることが、誰にでも可能であることもお分かりいただけたと思います。まずは、REISMの不動産投資セミナーをご活用いただき、不動産投資の知識を深めることからはじめてみてはいかがでしょうか。
関連記事:「不動産投資はやめとけ」の声には従うべき?やめとけの理由を探る