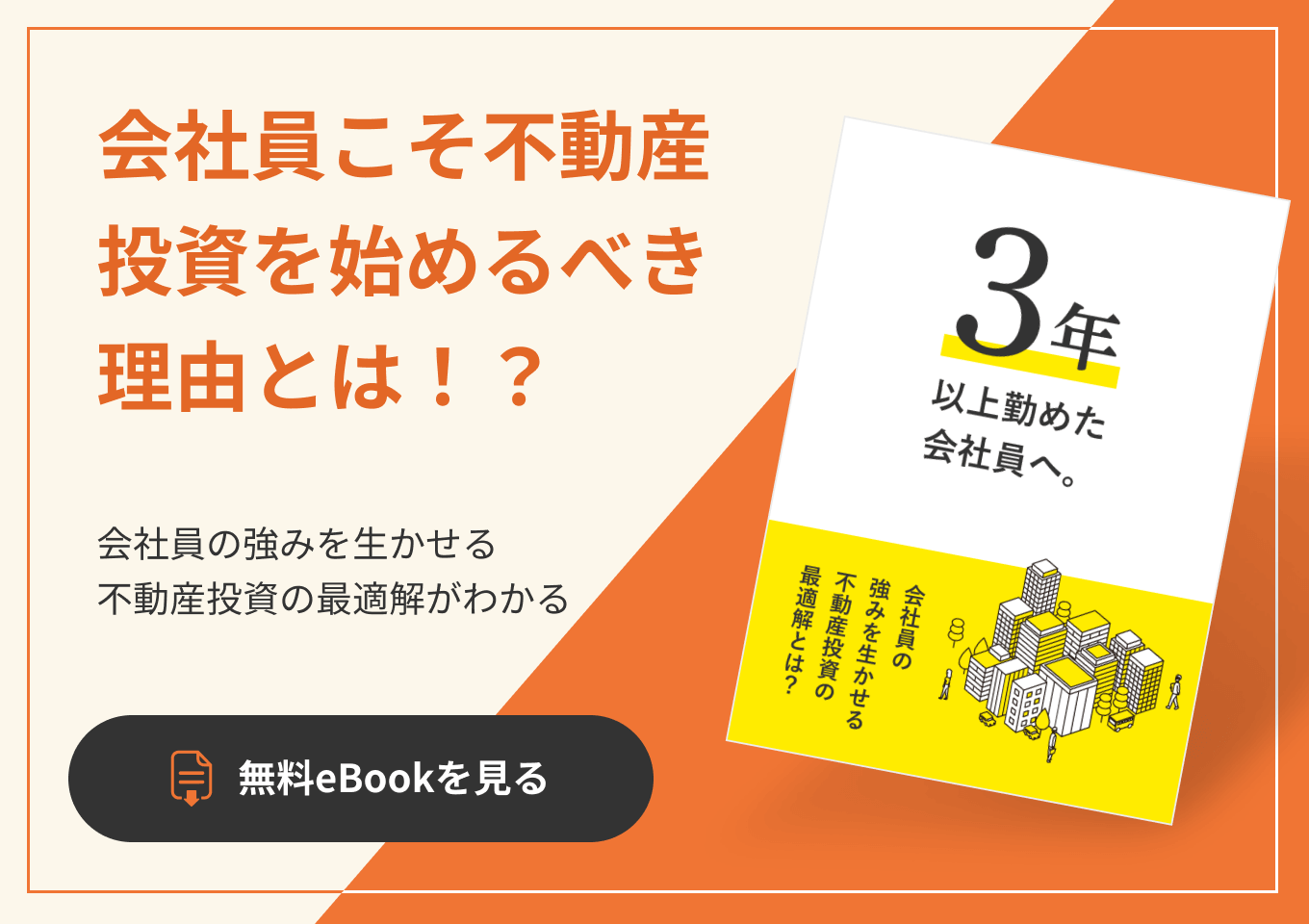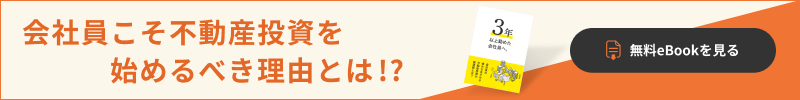副業禁止の大企業や公務員でも不動産投資なら大丈夫?
政府による「働き方改革」の推進で副業への注目が高まり実際に副業を始める人が増えているようです。しかし公務員や一部の大企業では、依然として副業禁止となっているため、「興味があっても取り組むことができない」という人も多いのではないでしょうか。
副業禁止規定がある職場でも不動産投資で得られる家賃収入については、多くの場合は副業とみなされず問題なく取り組むことができます。ここではサラリーマンや公務員の副業禁止規定と不動産投資について考えてみましょう。

不動産投資とはどういうものなのか?
一般的に副業というと、本業の他にどこかでアルバイトをしたり個人事業主として自分でサービスや商品を提供したりするなど、自らの労働で何かしらの価値を提供して収入を得ることをイメージするのではないでしょうか。しかし不動産投資はそのような労働が発生するわけではなく、購入した不動産を住居や駐車場として貸し出して賃貸収入を得ます。
毎月定期的に得られる家賃収入のことを「インカムゲイン」、不動産が将来値上がりして売却することで利益が得られた場合は、その利益のことを「キャピタルゲイン」と呼びます。不動産投資は株式投資や投資信託などと同様に利益を得て将来に備えるための資産運用の一貫ともいえるでしょう。
不動産を購入する際には不動産を担保にして金融機関から資金を調達し、購入資金に充てるのが一般的です。このような説明を聞くと「なんだか不動産投資は大変そうだ」と思う人もいるかもしれませんが、実態はイメージとは少し異なります。
不動産オーナーとしての仕事は購入物件の選定や物件のリフォーム、リノベーション、貸し出す際の募集広告、入居者審査、物件管理、家賃回収、毎年の納税などが主な業務です。しかしこのような管理業務のほとんどは不動産会社に委託できるため、オーナーの実務はほとんど発生せず負担は軽くすみます。

不動産投資が一般的な副業に当たらない理由
不動産投資での家賃収入は不労所得であり、日々の管理業務もほとんど委託できるので本業への影響は少ないと考えられます。また相続などやむを得ない事情で不動産を受け継ぎ家賃収入が発生するというケースもあるため、ほとんどの場合は大企業の社員や公務員に課せられる副業禁止規定には抵触しない傾向であると考えられていますが、不動産投資を始める前には必ず事前に勤務先の規定を確認する必要があります。
なお、一般的に不動産投資では5棟10室以上の規模(区分所有なら、おおむね10室以上、もしくは家屋が5棟以上)で運用を行うと事業的規模と見なされます。事業規模にまで大きくなると勤務先によっては副業認定されてしまう可能性も否めません。そのため不動産投資を行う前に就業規則などはきちんとチェックして注意するようにしましょう。
公務員の不動産投資も本当に大丈夫?
公務員の副業に関しては、大企業以上に厳しい印象があるので不安に感じる人もいるかもしれません。たしかに一般的なアルバイトなどの副業には非常に厳しいですが、事業的規模に当たらない限り不動産投資は問題ないと言えるでしょう。公務員の就業規則である人事院規則にも「営利企業の役員等との兼業の運用について」という部分で明記されているようです。
ただし事業規模と見なされる5棟10室基準に該当したり、賃貸に出される不動産が旅館・ホテル業、もしくは劇場や映画館、ゴルフ練習場などの施設に用いられていたりする場合は自営業と同じ扱いになるとして禁止されています。また、不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入が年額500万円以上である場合も同様の自営業扱いとなります。
副業として不動産投資を始める人の多くの場合は、区分所有のマンションやアパートから始めることが多いのでいきなり禁止されるような規模になることは少ないでしょうが、不動産投資を始める前には必ず会社の規定をチェックすることを忘れないようにしましょう。
公務員は安定した収入で社会的な信用度が高いため、金融機関の融資の審査も通りやすく資金調達面でもとても有利になります。自分の「属性」をうまく活用することも不動産投資では重要なポイントです。
本業が忙しくても始められる不動産投資ですが、まずは信頼できる不動産会社をパートナーとして見つけましょう。不動産会社によっては無料で参加できるセミナーなどを開催している会社もありますのでそのような機会を利用して不動産投資へのチャレンジを検討してみてはいかがでしょうか。