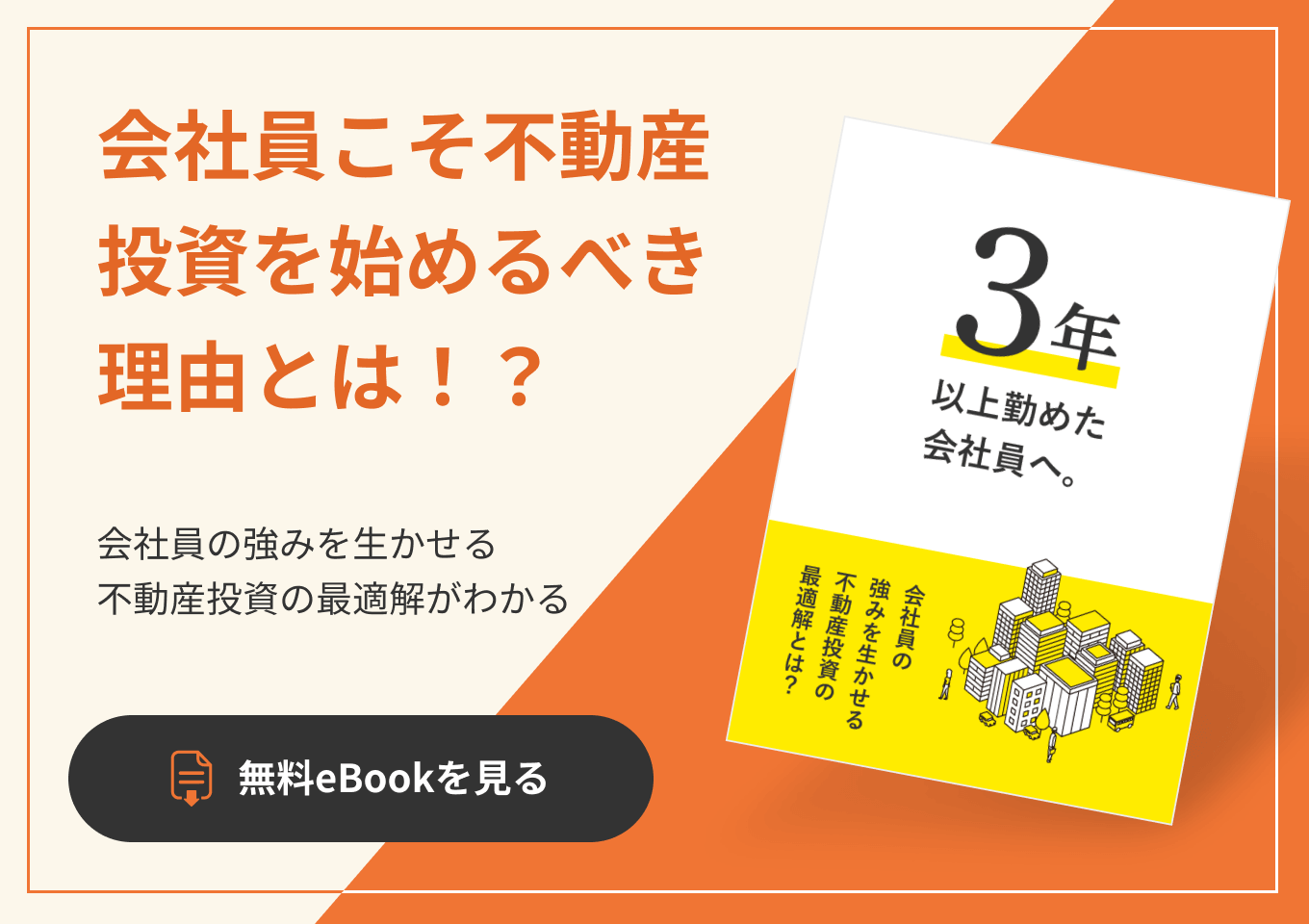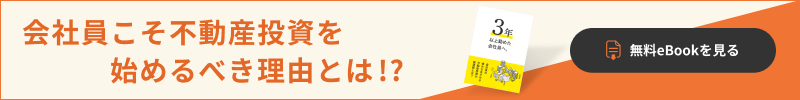不動産オーナーは高齢者の受け入れをどうするべきか
国内で今後さらに少子化や核家族化が進むと、一人暮らしの高齢者はますます増えていくでしょう。医療施設の多い都会では特に単身高齢者世帯が増えると予想されており、賃貸住宅を経営するオーナーにとっては需要増になるといえるかもしれません。ただ、単身高齢者世帯の場合、「孤独死」などのリスクがあります。これまで入居の申し込みがあっても敬遠するオーナーが多かったのも事実です。不動産オーナーは高齢者の受け入れについて、今後どう考えていけばいいのでしょうか。

都会に住む高齢者だけの世帯が増加する
2018年版高齢社会白書によると、2017年10月時点の65歳以上の人口は3,515万人で、総人口に占める割合(高齢化率)は27.7%です。つまり、すでに4人に1人以上が高齢者です。しかも、75歳以上は1,748万人(13.8%)と長寿化も進んでいます。現在20歳前後の世代が高齢者になる2065年には、65歳以上は約2.6人に1人、75歳以上は約3.9人とさらに高齢化が進むと予測されています。
現在の高齢者世帯は、3割が夫婦のみの世帯で単独世帯と合わせると半数を超えます。三世帯や子どもなどとの同居世帯は少ない傾向にあります。また、高齢者世帯は地方の割合が高く今後の伸び率も高まると予測されていますが、単純に人数だけでみると首都圏や近畿圏、中京圏に集中しています。
また、高齢者がいる世帯の82.7%が持ち家であるのに対し、単身高齢者世帯は65.5%で、持ち家比率は下がります。こうしたことからも、都会の賃貸住宅に住まいを求める高齢者が今後も増加していくと考えられます。
孤独死が最大のリスク
高齢の入居者が抱える最大のリスクは、やはり孤独死でしょう。孤独死とは、誰にも気づかれずに、一人きりで死ぬことであり、独居者が病気などの理由で急死して、しばらくしてから発見されるケースを指します。この言葉が広辞苑に初めて掲載されたのは2008年で、時代を映した現象といえそうです。また、2015年に東京23区内に住む単身高齢者世帯で孤独死したのは3,127人でした。2017年版高齢社会白書によると、孤独死を身近な問題だと感じる人の割合は60歳以上では17.3%ですが、一人暮らしに限ると45.4%にまで上昇するそうです。

見守りサービスやセンサーで早期発見
オーナーにとって最も大事なことは、入居者が死亡してから発見するまでの時間でしょう。その時間が長くなるほど、ダメージは大きくなります。死後1カ月以上経過してしまうと、それだけ原状回復費用が高くなります。また、遺体がそのまま放置されていたことによる悪臭などの通報で、近隣住民にショックを与えることにもなります。腐敗が進むとフローリングや壁を取り払うスケルトン工事が必要となり、次の入居者が見つかるまでに必要以上の時間を要します。こういった場合は「事故物件」として扱われるため、家賃の大幅ダウンにもつながりかねません。
こうした事態に対処するために、管理会社や警備会社に巡回してもらうこともできますが、すべてを防ぎきれるものでもありません。次善の策としては、入居者の了解を得た上で、中にいる人が一定時間動かなければ自動的に知らせる機能のついたセンサーを取り付ける方法などがあります。このほか、自治体や民間の見守り、駆けつけサービスを利用することもできます。
さらなるリスクヘッジとして、孤独死による損害を補償してくれる保険の利用を考えましょう。例えば、1戸あたり月に300円の保険料で、最大100万円の原状回復費用の補償に加え、最大200万円の家賃を保証している保険もあります。しかも、損失が認められなかった場合でも見舞金(5万円)の支払いを約束するなど、かなり手厚いといえるでしょう。
年金受給者の滞納は少ないためビジネスチャンス拡大
このように、高齢入居者を受け入れることと、孤独死のリスクは隣り合わせといえます。ただ、それを軽減するためのサービスや技術、損害保険なども充実してきました。高齢者は年金が支給されるので、家賃滞納は少なくなるといえそうです。少子高齢化が急速に進む中、持ち家を持たない高齢者を受け入れることは、社会的要請ともいえます。むしろ、ビジネスチャンス拡大と考えてリスクヘッジしながら積極的に受け入れることが、これからの不動産オーナーには求められているかもしれません。